お便りシリーズNo.54
= リベラリズム・プラグマティズム・懐かしのアメリカTV映画 =


【 リベラリズム・プラグマティズム・検証性 】
リベラルという言葉は、今日では非常に問題含みなものになってしまいました。たとえば、ネオリベラリズム(新自由主義)とは、自由経済を重視し、政府の介入は抑制されるべきとして市場を特権化する考えですが、これにはさまざまな批判があることはよく知られています。
しかし、歴史的に形作られてきた本来のリベラリズムの精神とは、個人の内的自由を国家や共同体などの自己以外の外的権威の抑圧・強制などから守ろうとするものでした。あらゆる外的権威に対し一定の距離を置き、批判的理性を行使し得る主体的個人を確立すること、それこそが本来のリベラリズムの骨法であろうと思います。
唐突のようですが、私はどんな個人であれ、組織であれ、国家であれ、そうしたリベラリズムの精神が包摂され、それが実際に機能することが闘争や競争的状況において勝者となる要(かなめ)であるように思います。
有名な政治学者の丸山眞男 (まるやままさお)は、戦後すぐに発表した論文『超国家主義の論理と心理』の中で、軍国主義下の日本の指導者たちの没主体性をするどく指摘しています。
それによれば、戦時下の日本の、権力と権威の一体化した超国家主義、その体制化における価値一切の国家による占有、社会のさまざまな組織や集団に広がる独善主義とセクショナリズム、その裏面としての階級の上下を問わぬ責任意識の希薄さと主体的意志の不在、そうした天皇制ファシズム下の社会の有り様が、冷静に客観的に分析されています。
日本はなぜアメリカとの破滅的な戦争を選んだのか、それは戦後日本の政治学者を突き動かした根本的な問いでした。戦争を体験した当事者として、自らの時代体験を思想化しようとした、その代表的政治学者が丸山眞男であったわけです。
その問いに対する丸山の回答は、戦前日本の統治体制における責任ある政治主体の不在だったと言います。後年の丸山の論文『政事の構造』(1983)によれば、日本における政事は上から下へ統治するのではなく、下から上へ自発的に協力して同方向に「献上する」のが、日本の「政事」の原型だとし、そう考えることで、たとえば議会が天皇の決定を「承認」するのではなく、「協賛」するという明治憲法の独特な規定も説明できると述べています。
しかし、その政事主体である天皇もまた奉られるばかりではなく、皇祖皇宗の神々を奉るかぎり、奉られる神は無限に遡及(そきゅう)し、究極の神は誰なのか、つまり究極の責任主体は誰なのか、最後まで特定できないという主体的意志の不在に帰着するというわけです。
私は太平洋戦争の戦史を読むたびに、当時の日本の天皇制ファシズムを駆動していた軍官僚たちの中に、この種の責任主体の不在、言い換えれば無責任の構造といった現象をいくつも見出すことができます。

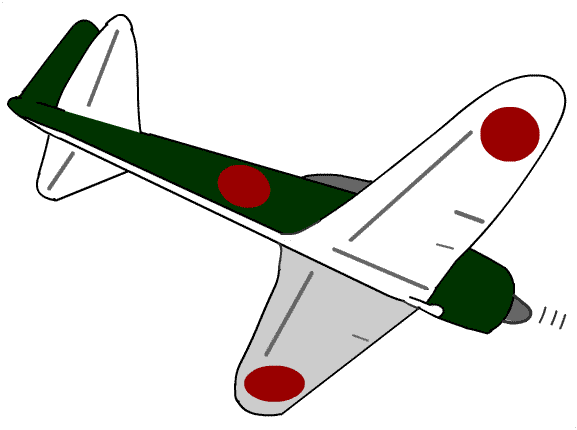
以前にも書いたことですが、たとえば昭和19年10月12日~13日にかけて戦われた「台湾沖航空戦」と呼ばれる戦いがあります。海軍側は当初、この航空戦で大戦果をあげたと確信し、天皇への上奏まで行っていますが、しかしこの戦果が全くの誤報であったことはすぐにわかってきました。
にも関わらず海軍側は、この戦果が誤報であったという事実を政府にも陸軍側にも伝えず、これを曖昧に処理したまま、結果的に隠蔽(いんぺい)してしまいます。
当初の日本軍の作戦計画では、あくまで陸上における「決戦」は、首都マニラのあるルソン島において行うものとされ、兵力配備およびその他一切の準備はこれを前提に進められていたにも関わらず、台湾沖航空戦の架空の大戦果を信じきった陸軍は、ルソン島のはるか南方にあるレイテ島において地上決戦を行っても日本軍に勝機はあると判断してしまいます。
こうして大岡昇平の小説などでも有名な、あの悲惨なレイテ島決戦が戦われるわけですが、日本軍はこの戦いに完敗します。
結局、終戦までにフィリピン全土で52万人の日本軍、日本人軍属、その他の民間の日本人が死にました(48万という説もあります)。一方的に戦場にされたフィリピン人は111万人が亡くなりました。これはフィリピン国民の16人に一人に当たります。(私の母方の叔母は、このとき日赤の従軍看護婦としてルソン島北部バギオから奇跡的にバシー海峡を隔てた台湾南部に脱出することのできた数少ない日本人の一人でした。)
昭和19年10月から翌20年8月までのわずか十ヵ月間のあいだに、なぜこれほどまでの膨大な人的損失があったのか、――中国大陸の日本人の戦死者が15年間で70万人だったことと比べてみても、わずか十ヵ月間で52万人という数字には慄然とせざるを得ません。
(注ーこの数字には戦争初期のフィリピン侵攻時の戦死者も含まれていますが、戦争末期の戦死者の数に比べれば比較にならないほど僅少です)
戦後、この大誤報の隠蔽に関わった海軍軍人は一様に「海軍という組織の空気に抗えなかった」、「自分には流れを変える権限がなかった」、「薄々おかしいと気づいていたが、今さら言い出すことはできなかった」といった類いの証言をしています。しかも驚くべきことに、この一大誤報事件に関して誰一人責任をとった形跡がありません。
当時の軍官僚といえば、一様に陸軍士官学校や海軍兵学校、東京帝国大学などを優秀な成績で出たスーパーエリートたちでした。しかしこのスーパーエリートたちが戦争指導の過程で、戦略的・戦術的な結果の有効性を追求せず、その場の空気や組織の論理や、盲目的な動機の純粋性だけを行動の規範とし、そしてその結果として悲惨極まりないほどの人的損失を招いたという事実は、今日的日本のエリート教育とも照らし合わせて深く考えさせられる事象です。
黙って状況をすくい上げ、なおかつその中で突出しない程度にベストな選択をする人材になれ、というのが日本的エリートの規範だとすれば、「空気が読めるか、読めないか」といった問題が強調される今日的状況は、組織のために誤報を隠蔽したかの海軍軍人と同じく、同質性へのプレッシャーの中で見事に協調的であるわけです。
そこに見出すものは行動の規範を自己の所属する共同体への利益か害悪かによって判断しようとする集団的功利主義、または「なりゆき」の現状を追認し、現実は我々が「起こす」行為の連鎖ではなく、「起きる」出来事の連鎖であるとする歴史的相対主義、自己の内面の命令によって行動し得る独立的な人格の不在であろうと思います。
ところで、プラグマティズムとは、その提唱者ウィリアム・ジェームス(1842~1910)にしても、その継承者ジョン・デューイ(1859~1952)にしても、何より人々が自分自身の運命の主人公であること、つまり行為主体である自己への信頼の上に立ち、個人こそが運命を切り開く主人公としての主体であることを強調する哲学です。したがって、決定論や運命論こそがプラグマティズムの哲学的ライバルでした。
同様に、日本的集団主義、なりゆき主義に対しても、個の立場が集団の同調圧力によって封印されてしまう点で、それに反対する立場です。(プラグマティズムが日本的集団主義へのアンチとして成立したという意味ではなく、論理的帰結として反対の立場に立つという意味です。)

ところで、そもそもプラグマティズムはなぜ個人の主体性を最も重視するのでしょうか?以下、やや迂遠な説明をしてみます。
「信念は経験によって検証され、最終的には習慣という形で定着する」というプラグマティズムの有名な定理は、逆に言えば人間の意志が問題になるのは、自らの習慣を自覚的にとらえ、これを何らかの仕方で変更しようとするときのみである、ともいえます。
このようなプラグマティズムの習慣論は、一般の日本人には意外なものに映るかもしれません。というのも、日本における習慣とは、変革よりはむしろ持続性や保守性と結び付けられて理解される傾向が強いからです。
しかし、この「社会変革の契機としての習慣」という考え方は、よく見ていけば極めてアメリカ社会の理に適ったものです。アメリカ社会は多様な文化的背景を持つ人々からなり、習慣もまた実に多様です。そして人々は自らのものとは異なる習慣を持つ人々の姿を、日々、直接的に目にし、さらにそこに経験における有効性が検証されれば、自分自身の習慣をも旧態にこだわらず変容させていきます。
その意味でアメリカ社会全体が多様な習慣の実験場であり、かつ習慣の担い手は主体的個人に託されているわけです。

たとえば、デューイは、その初期の論文の中でこんなことを言っています。
「たとえ人間ならざる権威が我々に何かを言うとしても、言われたことが真であるかどうかがわかる唯一の方法は、それが我々の望むような結果を与えてくれるかどうかを調べてみることだ。(中略)その唯一の方法とは、提案されたものが信念であるかぎりにおいて『善いもの』と判明するかどうかを功利主義的にためすことである。」とあって、つまり一つの世界観や価値観や社会的選択の基準といったものは、それ自体が根源的な意味において真であるか否かといった問いかけをすること自体意味をなさないというわけです。
その真正性は、その世界観や価値観や選択の基準の中で、実際に生きてみて、日常生活の中でそれらを使い、それらが我々個人や家族をより幸福にするかどうかを調べる、という仕方で試すことによって初めて明らかにされるとデューイは主張します。
教育学者としてスタートしたデューイは、各人が自らの運命の主人公となるための仕組みを模索し、一人一人が自らの生を通じて多様な構想を実験することを可能にする社会を目指しました。そのようなデューイにとって「実験としての民主主義」のカギとなるのが習慣でした。「習慣は第二の天性であり、習慣の方が十倍も天性である」というイギリスの軍人ウェリントンの言葉を、プラグマティズムの先駆者であるウィルアム・ジェームスはよく引用しますが、それは前提として、個人が主体的な自らの運命の担い手として自らを変革する力を有するという理念を信じるからです。
その意味で主体性とは、まさにプラグマティズムの基盤といえるわけです。
ここで経験による有効性の検証とはいっても、個々人がそれを「善きもの」「善き結果をもたらすもの」と経験する、その基準そのものが、そう一概に決まるものだろうかといぶかしむ人は、すでに集団内のドグマの調整をいかに成し遂げるかという意識が先行している点で早くも集団主義的であるわけです。他と共約可能な「社会的福祉」のようなものを除いて、本来個人の意見や政治的態度というものは、代表されたり委任することのできないものであり、
したがって、プラグマティズム的コミュニケーションの主要なモードとして要求されるものは、対立する利害の調整が第一義なのではなく、相異なる意見の交換そのものがきちんと保障されるということです。意見は意見と意見の交換の中で形成され吟味されるものであって、そうした交換の中でそれぞれの世界の見え方としてのドグマの差異というものは自然と際立ってくるものだと思います。
またそこには人々は行為し語ることを通して自らが誰であるかを示し、他ならぬその人の人格的アイデンティティーを能動的に表し、そうすることで初めて世界の中に現れるという考え方が前提にあるように思います。
これは言い換えれば、意見の表明や行為態度の表出に先行して人間的アイデンティティーが事前に内在しているとは考えないということです。現(あら)われに先行する自己の内面とは極めて分裂的・多義的で混沌としたものでしかありません。
よくコップの中の水が少しずつ溜まってきて、ある時点を越えると外側に溢れ出すといった表現が、自己と自己の内面の関係を例える比喩として使われますが、結局のところ、それは溢れ出たという現象の事実性に依拠して、そこから事後的に逆読みすることによって、コップの内面をも一貫したものととらえ直そうとする、あくまで事後的な操作なのではないでしょうか。
ともかく、低文脈な言葉による意志表明が決定的な意味を持つアメリカ社会において、意志表明以前に、あるいは行為態度の表出から離れて内在する個のアイデンティティーといった観念は、ほとんど受け入れられないものだと思います。
私が、民主主義とは制度上の問題ではなく、民のエートスの問題だと思うのは、いつも頭の中でこのようなブラグマティズム的な観念の無謬(むびゅう)性に固執しない自由さを備えた人たち、他者との意見の交換の中で、あらたに正しいと認知したことに対しては、素朴といえるほど正直であり誠実であろうとてする人々の行為態度を見出してハッとした体験を思い出すからです。
それは言い換えれば、討議の大切さを認識し、討議では自分の考えを訴えつつも、理に適ったことであれば『相手に説得されてもよい』という心的構えを持つ人々が有する、ある種の自由さとでもいうべきものです。
私が妻のローリーと共に6年間を過ごしたカリフォルニア・パロアルトのスタンフォード大学の人々や、その周辺のコミュニティーの人々の意見は、健全にばらけており、多彩であり、他者の意見に対して極めて率直でありながら、また実に柔軟でもありました。理に適った意見であれば、その意見を受け入れることに躊躇しない人たちでした。
私はそこに、空気や組織への依存に支配される日本的民主主義のあり方とはまったく違う社会文化を感じました。と同時に、そのような自立した個人主義的エートスを内在化させている社会の雰囲気に既視感のような不思議なシンパシー(sympathy)を感じました。
そのシンパシーの正体とは何なのか、のちにそれについて書いてみたいと思います。

ところで、社会学や政治学の世界では、具体的制度論でなければ何を語っても意味がないとする発想があります。そうした立場に立てば民のエートスの問題など単に〝心がけに気を配れ〟という程度の話にしか聞こえないのかも知れません。つまり、私の感慨など具体的には何も言っていないに等しく、「それがどうしたんだ」というような批判もあるでしょう。
しかし、本当にそうでしょうか?私はこのパロアルトの街とその郊外から生まれたアメリカ最先端のテクノロジー企業のいくつか、たとえばビル・ゲイツの「マイクロソフト」や、スティーブ・ジョブスの「アップル」、「ヤフー」、「グーグル」、「フェイスブック」、世界最大の衛星通信会社「インテルサット」(私たちはこの会社のチーフエンジニアの自宅に二年間部屋を借りて、家族同様に過ごしていました。)
そうしたいくつかの企業名を挙げてみるだけでも、まったく圧倒される思いになります。日本にもこのようなエートスに満たされた産業世界がどこかで生まれていれば、〝失われた二十年〟といった停滞もなかったのではないでしょうか。
2014年12月8日の日経新聞には、次のような特集記事が載せられています。
〔ロボ技術輸出か流出か〕
米グーグルが昨年、二人の日本人技術者が立ち上げたベンチャー企業「シャフト」を買収したとき、日本が直面する脅威が明らかになった。アップルやアマゾン・ドット・コムなど、米最先端のテクノロジー企業はロボット工学技術に高い関心を示している。
〈中略〉
東京大学のロボット工学研究の教授二人が設立した「シャフト」は、日本での投資家探しには失敗したが、グーグルが救いの神となった。「シャフト」の元最高責任者(CFO)加藤崇氏によれば、被災地でも作業できるように設計された同社製の不恰好な人型ロボットは、日本政府だけでなく国内のIT企業をまわった際にも一笑に付されたという。(ラインは木山)
「資金著調達は絶望的だった。だから僕らも踏ん切りがついてアメリカに行った。」と同氏は当時をこう振り返る。同社開発の二足歩行ロボットは、2013年12月に開かれた米国防総省高等研究計画局(DARPA)主催の高度な災害対応ロボットの競技会で優勝し、今年4月、米オバマ大統領は日本滞在中にシャフトによる災害対応ロボットのデモを見学した。
〈中略〉
シャフト元CFOの加藤氏は言う。「リベラルで技術がわかる人は、日本での活動が困難と知ると、シリコンバレーに行ってしまう。(パロアルトはシリコンバレーの頭脳的中心です。)日本で〝なんだお前〟と言われるような人材がアメリカに行った途端、神様のように扱われる。」

【 懐かしのアメリカTV映画 】

昭和30年代は日本の大衆テレビ文化の黎明(れいめい)期でした。(日本でテレビ放送が始まったのは昭和28年のことです。)そしてこの時代は不思議な日米の文化的混血の時代でもありました。おもしろいことにテレビに出演する芸能人の名前も、どこかハワイあたりの、白人と混血した日系人のような響きがあり、「ジェリー藤尾」とか「ペギー葉山」とか「トニー谷」といった、そんな感じの名前ばかりでした。そして圧倒的に数多くのアメリカ制のテレビドラマが放映されており、人気も非常に高かったのです。
子供であった私の目にも、日本製の番組よりアメリカ製のドラマの方が質的に上だと感じました。母は「ルーシー・ショー」のルーシー役(ルシル・ボール)がお気に入りで、この五十年代のアメリカのホームドラマを楽しみに観ていました。私は小さい時は「名犬ラッシー」が好きで、ひたすらコリー犬が欲しくなった時期があり、子供向け西部劇の「ローン・レンジャー」を観ては、目のまわりだけを黒いマスクで隠したローン・レンジャーの姿に憧れました。
そのほかにも、「イルカのクリッパー」、「うちのママは世界一」、「ローハイド」(ローレン、ローレン……とくり返す冒頭の歌詞が有名)、ワーナー映画と協力関係にあったアメリカABCテレビが製作した「ディズニーランド」は、特に大好きで、時々父を喜ばすプロ野球中継に番組が変更されてしまうと、子供ながらに本気で恨めしく、非常に悔しい思いをしていました。
アニメーションでは「トムとジェリー」とか「ポパイ」、人形劇の「サンダーバード」、「潜水艦スティングレー号」、マフィアとの戦いを描いた硬派のドラマ「アンタッチャブル」、名医「ベン・ケーシー」、リチャード・キンブルの「逃亡者」も絶大な人気でした。
いつも番組の冒頭には「職業医師リチャード・キンブルは妻殺しの罪で刑務所に護送中、列車事故でからくも脱走。髪の色を染め、彼は逃げる、今日もそしてまた明日も……」といった長いナレーションがあって、「彼は逃げる、今日もそしてまた明日も」の部分は、ほとんどの小学生が色々なシチュエーションに置き換えては冗談に使っていました。
1950年代から60年代にかけて少年少女時代を過ごした多くの日本人が、これらのアメリカ製テレビ映画から何らかの思想的影響を受けていることは否定できないと思います。
しかもこれから述べる戦争ドラマ「コンバット」の例でいえば、アメリカのテレビ放映の開始が昭和37年(1962)の10月2日、日本で第一話が放映されたのが同年11月7日でしたから、約一ヶ月間の差しかありません。
一般の日本人が海外に旅行することなど夢のまた夢であった時代にあって、その遠く離れたアメリカ国民と日本人とが、ほぼリアルタイムといっていいほどの時間差で同じテレビドラマに心を動かされ、見入っていたという事実は、私には大変印象深いことのように思われます。
あの時代が日米の文化的混血の時代であったと思うゆえんです。


昭和30年代といえば、一般庶民の家庭にはイスもテーブルもまだ珍しく、だいたい四畳半ぐらいの茶の間とちゃぶ台の食卓、冬は炬燵(こたつ)、部屋の角隅に置かれた白黒テレビ、アンテナはテレビのすぐ上からウサギの耳のように突き出ていました。ガスコンロはあったものの、庭の七輪で魚を焼いたり、石炭でお風呂を沸かしたりといった、そういったいわば昭和の原風景のような中で、子供であった私はWASP(ワスプ=白人・アングロ・サクソン・プロテスタント)的なアメリカ社会の価値観や生活様式を、テレビのブラウン管を通してほぼリアルタイムに受け取っていたことになります。
しかも質的に高いものからは、より深い影響を受けます。ちょうど同じころ人気を博していた日本製のテレビ番組「てなもんや三度笠」(藤田まこと・白木みのる・財津一郎)や、トニー谷の歌謡番組などから、何かしらの思想的影響を受けたかといえば、即座に「それはない」と言い切れますが、アメリカのテレビドラマからはやはり強い影響を受けたのだと思います。
たとえば、往年のハリウッドビューティーの一人、ドナ・リード主演の「うちのママは世界一」は1950年代末の典型的なアメリカ中産階級のホームドラマでしたが、そこには特定の価値観というか、もっといえばイデオロギーとでもいえるべきものが明確にありました。
やはりこの種のホームドラマは、アメリカ社会の理想とか秩序のようなものをブラウン管を通して一般家庭に浸透させていく意味合いが強かったように思います。
1950年代末といえば、黒人の公民権運動の盛り上がりが、アメリカ社会全体を騒然とさせていた時代であるにも関わらず、そうした人種差別などの深刻なテーマは注意深く避けられていました。ママ(ドナ・リード)を悩ます問題は常に家庭内の些細なヒューマンなトラブルに限られ、しかもいつも30分以内に首尾よく解決されていくのでした。1957年アーカンソー州のリトルロック、セントラル高校での9人の黒人生徒入学をめぐる衝突では、アメリカ連邦軍が出動するといった、そうした騒然とした時代にあって、アメリカンホームドラマは一見してWASP(ワスプ)とわかる家庭をドラマの中心に据えることで、国民の意識を小さなコミニュティー世界に封じ込めることに腐心(ふしん)していたともいえそうです。
しかし、そうした情報操作の一面はあったにせよ、それでもママ役のドナ・リードは優しく知的でイノセントな良き時代のアメリカ人女性を見事に形象化していました。

1962年(昭和37年)に登場した一連の番組の中で、最大のヒット作は第二次大戦中のヨーロッパ戦線のアメリカ陸軍分隊の戦いを描いた戦争ドラマ「コンバット」でした。軽快なマーチ風のテーマ曲や、銃弾で描かれる〝COMBAT〟のタイトル、ヴィック・モロー演じるサンダース軍曹の乾いた渋い声(もちろん日本人声優の吹き替えでしたが、実によくマッチしていました。)、分隊メンバーのカービー、なぜか身体の大きなリトル・ジョン、ケリー、カーター、それからサンダースの上官であったヘンリー少尉など、懐かしく思い出す現在50歳代後半の方も多いのではないでしょうか。
当時の日本製戦争映画がミニチュアや特撮技術を多用することによって、逆に安っぽいものに見えてしまったのに対し、コンバットの映像の質感は、兵士の持つライフルやマシンガン、ジープやハーフトラック、さらにはドイツ軍の軍装兵器にいたるので、実にリアリティーがありました。少年時代から軍事マニアであった私が夢中になったのは言うまでもありません。
しかし、一般的な「コンバット」人気の最大の理由は、何といってもサンダース軍曹の人間的魅力に尽きました。実はシリーズの初めはリック・ジェーソン扮するヘンリー少尉の方が主役だったのですが、回を重ねるうちに、助演であったヴィック・モローのファンが増えていき、サンダース軍曹の出番の方が多くなったのでした。ヴィック・モローという独特な個性がサンダース軍曹というキャラクターに人間的な幅とふくらみを与えていました。そして時には人間臭く、時には果断に部下たちをリードしていく軍曹の姿に、ファンはあの時代の理想の男性像を見出していたのだと思います。
私にとって特に驚くべきことであったのは、サンダース軍曹が分隊メンバーに対して、あたかも優れた教師のように振舞っていた点です。彼は分隊メンバーの意見をよく聞き、耳を傾け調整し、その上で自身の判断を下していました。それは私が少年のころ、戦争帰りの叔父さんたちに話を聞いて、漠然と抱いていた旧日本軍に対する印象――上官の命令には絶対に服従し、その当不当を論じたり理由を質問することを許さず――といった極めて強力な規範やしゃちこばった精神主義、またそれを犯すことによって被るであろう隊内での私的制裁への恐怖といったものとはまったく無縁の世界でした。
そして、このような行為態度が、決してテレビ用に作られた架空のものではなく、現実のアメリカ軍の中にも、あるべき上官の姿としてとらえられていたということを後に知りました。
アメリカ軍の統率の原則は、部下を保護することが指揮官の務めであり、部下を保護した上で率先垂範を実行するのが彼らの統率の原則でした。この部下の保護と率先垂範を合わせたアメリカ的な表現は、「自分ならしないこと、あるいは自分がしたくないことを部下にさせない」ということになります。
以前にも書いたことですが、アメリカ軍の兵士たちは、命令が理不尽だと感じたり無理だと思った場合には、率直に指揮官に反対したり、意見具申をしたり、あるいは無言の抵抗をしたりと、何らかの形で反発することができました。どんな無茶な命令にも盲目的に服従することは、アメリカ軍兵士の美徳とはされませんでした。
この傾向はとくに州兵基幹部隊において顕著であり、民兵制の伝統を持つ州兵部隊では、指揮官も民主的に選出されていたという事実は、以前のお便りシリーズにも書きました(お便り№47)。アメリカ社会における意志決定の仕方も一般的には様々な情報を各自が共有した上で意見を出し合い、論議の末、多数の支持する方針が決定されます。州兵部隊の下士官たちも部下の意見を聞いたうえで最終的に意志決定をしていました。「話し合い、意見を聞き、率直に議論をする」ことが彼らの意思決定の方法であったと、第二次大戦に従軍した多くのアメリカ軍下士官が証言しています。(〈玉砕〉の軍隊、〈生還〉の軍隊 講談社 選書メチエ203のP229)

このことを逆にいえば、米軍の下士官たちは作戦指揮能力に欠けるにも関わらず、階級を笠に着て命令を出したり、部下を危険にさらしたりする、つまりは「階級をひけらかす」将校をもっとも嫌っていました。階級だけ高くても技能が伴わない場合、そのような「権威の葛藤」状態が生じる場合の、とくに深刻な状況では、上官への「反抗」が現実のものとなりました。
たとえば、上官の命令に対する意図的なサボタージュや不服従といった無言の抵抗から、部下である下士官に一時的に指揮権を委譲するよう迫る委譲戦略や、さらに上級指揮官への意見具申や直訴などのさまざまな戦略がとられました。
そのもっとも甚だしい場合には、部下たちの気に入らない上官が手榴弾によって爆殺される「フラッギング(FRAGGING) 意訳すれば上官殺し」にいたります。アメリカ国防省の記録によれば、ベトナム戦争の激戦が続いた1969年に96件、1970年には209件の「フラッギング」が起きており、それぞれ39名、34名の犠牲者が出ています。
どんな組織であれ、インフォーマルな集団の形成と、そこで共有されるインフォーマルな規範VS公式な組織の規範の齟齬(そご)といったものが、多かれ少なかれ存在しました。これはアメリカ軍の抱える闇の部分と言えます。
しかし、その暴力を伴う「私的制裁」の方向は、あくまで下から上へのベクトルであり、旧日本軍の組織文化を象徴する上官による下級者への私的制裁とは方向が逆である点に注意すべきです。日本陸軍の内務班生活に象徴されるような上官による私的制裁は、日本軍組織における、いわば一種の病理現象であって、かつて丸山真男は「抑圧委譲の原理」によって、この病理現象を説明しようとしました。
つまり階級社会の軍隊においては、上官の命令は絶対であり、下級者には反論の余地はない、下級者は上級者からつねに押さえつけられているから、その自己が経験した押さえつけ、すなわち「抑圧」を自己よりも下の者へ順繰りに与えていくというのが丸山の言う「抑圧委譲の原理」でした。
こうした指摘に対し、私的制裁は精強な兵士を養成することを目的とした軍隊組織の「軍事的合理性」の追求の結果であるとする意見もあります。実は日本軍は一面において非常に組織としての合理化が進み、米軍組織よりもはるかに堅い「官僚制化」の進んだ組織でした。言い換えれば、一つの目的合理性以外の柔軟な応用性に欠ける組織でした。
どのような組織であれ「官僚制化」が過度に進展すると、逆機能としての弊害をもたらします。その一例が兵や下士官の意見を幅広くくみ上げ討議し、新たな戦術を創出するシステムの欠如でした。
結局のところ、戦闘組織の軍事的合理性の追求とは、それぞれの軍隊組織の置かれた社会や文化的文脈に依存するといえます。白兵主義を金科玉条(きんかぎょくじょう)とし、それを究極の目的合理とする日本陸軍の場合は、厳しい官僚制的軍隊の道を歩むことになりました。
逆にリベラルな開かれた討議を重視し、柔軟な戦術の展開を追及しようとすれば、アメリカ軍のような民兵的軍隊の名残りを強く留める組織になるのだといえます。
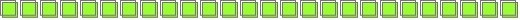
【プラグマティズム的分析と信賞必罰による
ダイナミックな人事】
戦場で実績を示した者よりも中央官衙の勤務経験を優遇する経験が強かった旧日本軍の人事に対し、アメリカ軍の場合はかなりオープンドライな思い切った抜擢(ばってき)人事を行っています。
たとえば、太平洋艦隊指令長官であったチェスター・ミニッツは、少将から中将を跳び越して大将に昇任していますし、日本本土初空襲を成功させたドーリトルは、最初予備役の少佐であったものが、たった三年で中将にまで昇進しました。
日本軍の場合、少将をすぐさま大将にすることは、軍の内規上、不可能でしたし、少佐が三年で中将になることなども有り得ないことでした。
こうしたオープンな感覚は、一民間人の軍への提言であっても、それがプラグマティズム的結果の有効性を保証するものであれば、大胆に戦術や兵器の開発に反映させていくといった柔軟性にもつながっていきます。
以前にも書いたことですが(お便り№51)、たとえばリンドバーグ(lind・bergh)といえば愛機「スピリット・オブ・セントルイス号」に乗り、ニューヨーク~パリ間の大西洋無着陸横断飛行に成功した空の英雄ですが、おもしろいことに彼は後の太平洋戦争の最中、陸軍の戦闘機P38ライトニングのプロペラピッチと過給器の調整により、航続距離を二割増しに伸長させるアイデアをもって、当時日米の激戦地であったソロモン諸島のアメリカ軍基地を巡回しています。
時の米軍指導部はリンドバーグのこのアイデアに飛びつき、彼に大尉の肩書きを与えて便宜を図っています。一民間人でしかなかったリンドバーグであっても、それが理に適ったアイデアであれば一民間人としても軍を教導できたという事実は、当時のアメリカ軍の実に柔軟な体質を物語っています。
またアメリカ海軍に無線傍受を不可能にする可変周波数通信のアイデアを持ち込んだのが、当時のハリウッドの美人女優であったことは有名な戦争エピソードの一つですし、もちろんアメリカ海軍はのちにこれを取り入れ実用化しています。
私はこうしたリベラルな空気とプラグマティズム的検証の中から、アメリカ軍が当時世界のどの国も持ち得なかった革新技術をものにしたこと――たとえばTV真管付きの砲弾や高度に統合された強襲上陸システムの創出や空母を中心としたレーダー管制の編隊空戦による迎撃システムなどを生み出した背景であったと私は信じています。
ところで、官僚制化の強い組織においては、〝結果の有効性〟といったプラグマティズム的検証の精神がなぜなおざりにされる傾向が強まるのでしょうか?
そもそも「官僚主義」とは、官僚制に特有の行動様式や精神構造を指す用語であって、特に一定の思想内容を持つものではありません。しかしその外面的特色としては、秘密主義、わずらわしい手続き主義、先例踏襲主義、画一主義、形式主義、創意の欠如、派閥主義、縄張り根性、役得や利権の利用またはそれに立脚した傲慢さ、などを挙げることができます。
やはり官僚の官僚たる所以(ゆえん)は、何といっても自己の所属する課や局や省庁が、いかに他の干渉を排して自分たち自身で行政を主導できるかという点にあります。それは具体的な行動としては、人事権と予算をどれだけとれるかということです。そのことが究極の勝負であり、最大の関心事であって、その点で派閥主義や縄張り意識が強いわけですが、一方でその予算や人事で何が起きたかについては、つまり結果の有効性については、あまり関心がない――というのは言いすぎだと思うかもしれませんが――少なくとも予算や人事権の獲得に費やす執念ともいうべきエネルギーにくらべれば、比較的に関心が薄くなってしまうというのは、個々の人間の資質うんぬんというよりも官僚というものが不可避的に身につけてしまう体質・DNAのようなものだと私は思います。

ところで、ある程度組織が大きくなった大手予備校などの人事・業務にもこの手の官僚的先例主義、画一主義、派閥主義などが見受けられます。私自身、所属する組織内の保身や既得権に関わると知った瞬間、論理的には間違いとわかっていながらも、黒をも白と言いくるめてしまう事務方の官僚的答弁に困惑苦笑したことがたびたびありました。
又は、逆に如才なく「 いやー、先生のおっしゃることはご無理ごもっとも、先生のおっしゃる通りでございます!」と言ってくれる事務方であれ、いや、むしろそう言う人に限って現実には事態はまったく動かないものであるということもしっかり学びました。
たとえコップの中の嵐程度の狭い組織ではあっても、そこには瑣末な政治的力学があり、それに連動して動く官僚的処世があり、いくら真っ当ではあっても素朴な論理ではいかんともし難い壁のようなものが存在します。
そうした自己の経験からも、私はやはりどんな個人であれ、組織であれ、国家であれ、先に縷々(るる)述べたようなリベラリズムの精神が包摂され、それが実際に機能することが、個人や組織間の闘争や競争的状況において勝者となる要(かなめ)であるとしみじみ思うわけです。
私はアメリカの友人たち中に、他者との意見の交換の中であらたに正しいと認知したことに対し、素朴といえるほど正直であり誠実であろうとする人々の行為態度を見出してハッとした体験が何度もありました。それは言い換えれば、討議の大切さを認識し、討議では自分の考えを訴えつつも、理にかなったことであれば『相手に説得されてもよい』という心的構えを持つ人々が有する、ある種の自由さとでもいうべきものです。そしてそれは彼らの強さの秘訣でもありました。
われわれ日本人もこうしたリベラルな精神をもう少し身につけたらどうでしょうか? 自己の内面の自由が、組織や共同体内の自己のポジショ二ングによる外的同調圧力によって捻じ曲げられてしまうことほど気持ちの悪いことはありません。
ですから、そうせざるを得ない状況にある人、例えば「ご指摘は確かに論理的にはその通りでありますが、組織の営利上、それをそうだと認めるわけにはいきません」と言わざるを得ない人にはその心中を察して心から同情します。しかし、一方では理にかなったことなら互いに率直に認め合った方がそこから新しい方向性が生まれたり、組織全体の活性化・強化につながったり、長い目で見ればむしろよい影響もたくさんあるんですよとも言いたいのです。

もどる