お便りシリーズNo.80
= 令和6年・2024年
東京大学古典だより(古文漢文) =

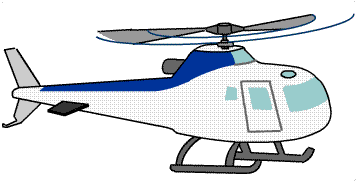
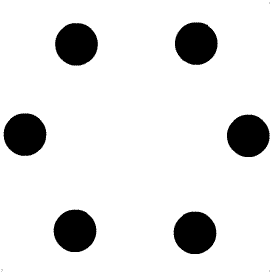
死を凝視する眼差し
ルポルタージュ(記録文学)
例えば,肉親の死を看取る際、死がその人の身体にしだいに這い上がってきて、肉体の崩壊が顕(あらわ)になってくる時、せめてもの栄養を口から通してあげようとする、としましょう。栄養剤の入った冷たい果汁などを吸飲みに入れて、ごくわずかづつでも、ようやく飲んでくれた、と見る間に、口に含んだものを喉へ通すのが急に嫌になるのか、ブァーッと歯の根の間から液が溢れ出てきたりする。もはや、その人でありながら、その人でないような感覚に、看取りをする側も思わず狼狽する。
死にゆく人は、慈しみ育んだ我が子か、長年の苦楽を共にした愛する伴侶か、恩愛の情深き敬愛する父母か、たとえ誰であれ、死がその身体を破壊し続けて、尋常あらざるものに変えていったとしても、看取りをする者にとっては、それでも、その身体は大切なものであり、大事な、かけがえのない、かえ難いものであり、いかにむごい姿をみても、肉親であればこそ最後まで見届け、なお名残を惜しみたいと痛切に思うのではないでしょうか。
なぜ、こんな話をするのかと言えば、このような痛切極まりない看取りの現場の感情を、和歌は表現し得るものなのか、と自問してみたくなるからです。現代短歌は分かりません。しかし、少なくとも古典和歌においては、死後の哀傷は表現出来ても、看取りの臨場の感情をすくいとるような構造にはなっていないのではないか、と私は思います。
『讃岐典日記・上巻』は堀河天皇の発病から崩御までの看取りの記録ですが、実は、上巻には作者の自作の和歌は一つも出てきません。
再出仕後の約一年間の追憶の日々を描く下巻にも、自作の和歌はわずかしか入っていません。 古典和歌における哀傷歌の伝統は ” 死なれた者の追憶の歌 " であり、季節の推移の景に触れて亡き人を偲ぶというスタイルです。そのような表現形式は、看取りの現場に臨場した者にとっては、いかに美しく哀切ではあっても、あまりに叙情的であり過ぎて、看取りの痛切な現実からは遠いものと感じられたのではないでしょうか。
和歌では汲み取れないものとして、そのかわりに、作者の表現の焦点にあるのは、即物的なまでの堀河天皇の身体に関する強い執着、死を観念的に捉えるのではなく、物質的肉体的な変化に即して実に細やかな描写により臨終を表現しようとする態度でした。そのことが、『讃岐典日記』という作品を唯一無二の作風としているのですが、この作者の即物的視点がどこからくるのか、私も2年前、93歳の父の死を看取った経験から、少し思うところがあり、その点を述べてみたいと思います。《ただし、私が父の看取りに関わったのは最後の十日ほどであり、最後の1年間父を支えたのは私の母でしたから、以下に書くことは母の視点からの考察です》
かつての日々には父の身体は父のものでしたが、死がしだいに父の身体に這い上がってくる過程では、父の身体は父のものとも母のものとも次第に不可分なものとなっていったように思います。特に最後の数ヶ月は、母にとっての父の肉体は、朝晩世話をし慣れたこの手この足であり、毎日拭いてあげた胸であり、さすってあげた手足であり、抱え起こす肩と背中であり、梳(す)いてあげた髪であり、割り箸の先につけた脱脂綿に水を含ませて飲ませた口であり、ゴクリと動く喉仏であり、骨太なだけにげっそりと肉が萎えた胸や肋骨の動きにも、死にゆく人の肉体に対する強い執着が否応なく母の胸に迫ってくるような、まるで死にゆく者と看取る者とが肉体の上で深く一体化しているような感じに見えたものでした。《実際、母は他の誰も気づかないような父の容体の変化をめざとく見つけては、ぼんやりしている私たちを何度も慌てさせたりしました》
こうした看取る者の視点、つまり臨終の肉体への強い執着を伴った視点が、『讃岐典日記』では結果的に ”冷徹な観察眼 " となって現れるのですが、では、当の本人が冷静かと言えば、むしろ真逆で、無我夢中の懸命さの現れとも言えるのではないか、と私は母の経験を通して、そう思います。
よく、学者の批評の中には「死の悲しみを自ら抑圧した結果」とか、「異様なまでの冷静な眼差し」などと書かれることもありますが、作者が著したような死に行く肉体への強い執着、時には感情よりも先に発現する、肉体上の変化に対する鋭敏な眼差しというのは、ごく身近で看取りする者にとっては自然な帰着なのではないでしょうか。
ここで『讃岐典日記』について、もう一つ別の問いを立ててみましょう。それは「はたして讃岐典日記上巻は文学作品なのか?」という問いです。無我夢中の懸命さで、堀河天皇の肉体の崩壊と死を看取りの現場で凝視し続けた文章は、はたして文学作品と言えるのでしょうか? その問いは、宮沢賢治が死の床で書きつけ、死後三日目に枕の下から発見されたメモ書き『雨ニモマケズ』がはたして詩なのか、という問いと同じ意味合いの問いです。
確かに、文学作品としては平安時代の他の日記作品に比べて見劣りする、とよく言われます。しかし、文学的であるかどうかを問わず、一編のルポルタージュと見れば、これほど感動的な《または衝撃的な》古典作品は他に類をみません。まさに唯一無二の作品です。
当時は神と同じレベルで語られていた天皇の死を、一介の人間の死として、ここまで克明に描き切る作品は他に例がありません。堀河天皇の手足の腫れと浮腫み、身体のだるさに耐えかねて氷室(ひむろ)から取り寄せた氷をボリボリと食う姿、病気の苦しみからくる周りの女官たちへの癇癪、いよいよ臨終が迫った時の激しい咳きの発作と「天照大神、われを助けたまえ」の絶叫、南無阿弥陀の念仏を唱えながらしだいに動かなくなる天皇の口びる、瞳孔が開いたドロンとした眼(まなこ)のさま、冷たくなる手足、蘇生を試みて摩(さす)る手足がしだいに死後硬直で固くなっていくさま、これらは寸分の余裕もなく、愛する人の肉体の崩壊へのやむにやまれぬ執着心が書かせたものである、と私は思います。
天皇の死後、他の女官たちがご遺体にすがって泣くのを見ても、作者は泣けない自分に気付きます。なぜ泣けないのか? おそらく作者は『泣く側の女官たち』と一体ではなく、『泣かれる側の堀河天皇』と一体化した意識を持っていたからではないでしょうか。天皇の愛妾として最もおそば近くに添い臥し、天皇の生き身をどんなに大事に思ったかしれない作者を、天皇は時にいたわり、時に突き放したり、叱責したりと、看取りの日々は生やさしいものではなく、そうした心の行き交いの中には、他者の介在の余地のない、二人だけのものがあったのではないでしょうか。少なくとも、作者自身はそう思っていたのではないでしょうか。
今回の東大の出題は、下巻の冒頭、白河院からの新帝へ再出仕すべしという強い要請があったという箇所から始まっています。作者は出仕をためらいますが、それはたんに " 二君に仕えることをいさぎよしとせず ” という倫理的理由というより、以上述べたような「他の誰よりも堀河帝を身近で看取ったのは私なのに、なぜ、よりによってその私が・・」というような気分ではなかったか、と想像します。
《私の思い出》
20代後半の頃、熊本県立図書館の書架の間で、たまたま読み始めた『讃岐典日記上巻』があまりに衝撃的で、一気呵成に読み終えた思い出は忘れられません。
窓ガラスの向こうから辺りを圧する程の蝉しぐれの音が聞こえていましたが、堀河天皇の発病と死も、盛夏の京のうだるような暑さの中でのことでした。
私には、やはり名作です。


第二問(古文)
次の文章は『讃岐典侍日記(さぬきのすけにき)』の一節である。堀川天皇は病のため崩御し、看病にあたった作者も家で裳に服している。そこへ、女官の弁の三位(べんのさんみ)を通じて堀川天皇の父白河上皇(院)から仰せがあった。新天皇は、幼い鳥羽天皇(堀川天皇の子)である。これを読んで、後の設問に答えよ。
かくいふほどに、十月になりぬ。「弁の三位殿より、御文」といへば、
取り入れて見れば、
「ア 年ごろ、宮づかへせさせたまふ御心のありがたさ
など、よく聞きおかせたまひたりしかばにや、院よりこそ、この内にさやう
なる人の大切(たいせち)なり。登時参るべきよし、おほせごとあれば、
さる心地せさせたまへ」とある、見るにぞ、あさましく、ひがめかと
思ふまで、あきれられける。
おはしまししをりより、かくは聞こえしかど、いかにも御いらへのなかりし
には、さらでもとおぼしめすにや、それを、
イ いつしかといひ顔に参らんこと、あさましき。
周防(すはう)の内侍(ないし)、後冷泉院(ごれいぜいいん)におくれまゐらせ
て、後三条院より、七月七日参るべきよし、おほせられたりけるに、
天の川おなじ流れと聞きながらわたらんことはなほぞかなしき
とよみけんこそ、げにとおぼゆれ。
「故院の御かたみには
ウ ゆかしく思ひまゐらすれど、
さし出(い)でんこと、なほあるべきことならず。そのかみ立ち出でしだに、
はればれしさは思ひあつかひしかど、親たち、三位殿などしてせられんこと
をとなん思ひて、いふべきことならざりしかば、心のうちばかりにこそ、
海(あま)の刈(か)る藻(も)に思ひみだれしか。
げに、これも、わが心にはまかせずともいひつべきことなれど、また、
世を思ひすてつと聞かせたまはば、さまで大切にもおぼしめさじ」と
思ひみだれて、いますこし月ごろよりももの思ひ添ひぬる心地して、
「エ いかなるついでを取りいでん。
さすがに、われと削(そ)ぎすてんも、昔物語にも、かやうにしたる人をば、
人も『うとましの心や』などこそいふめれ、わが心にも、げにさおぼゆる
ことなれば、さすがにまめやかにも思ひたたず。
オ かやうにて、心づから弱りゆけかし。
さらば、ことつけても」と思ひ続けられて、日ごろ経(ふ)るに、
「御乳母(めのと)たち、まだ六位にて、五位にならぬかぎりは、もの参らせぬ
ことなり。この二十三日、六日、八日ぞよき日。とく、とく」とある文、
たびたび見ゆれど、思ひたつべき心地もせず。
「過ぎにし年月だに、わたくし
のもの思ひののちは、人などにたちまじるべき有様にもなく、見苦しく
やせおとろへにしかば、いかにせましとのみ、思ひあつかはれしかど、御心の
なつかしさに、人たちなどの御心も、三位のさてものしたまへば、その御心に
たがはじとかや、はかなきことにつけても、用意せられてのみ過ぎしに、
いまさらに立ち出て、見し世のやうにあらんこともかたし。
君はいはけなくおはします。さてならひにしものぞとおぼしめすことも
あらじ。さらんままには、昔のみこひしくて、
カ うち見ん人は、よしとやはあらん」
など思ひつづくるに、袖のひまなくぬるれば、
キ 乾くまもなき墨染めの袂(たもと)かなあはれ昔のかたみと思ふに
現代語訳
このように言ううちに(=そうこうするうちに)、十月になった。「弁の三位
殿《注…鳥羽天皇の乳母》より、お手紙」というので、取り入れて見ると、
「ア 年ごろ、宮仕えせさせたまふ御心のありがたさ
などを、良くお聞きになっていらっしゃったからなのでしょうか、院より、
この内《注…鳥羽天皇の御所》にそのような人が大事である。
登時《注…とうじ=すぐに》参上して仕えよという仰せ言がありましたので、
(あなたも)そのようなお気持ちでいて下さいと書いてある、(それを)見ると、
驚きあきれる程に意外なことで、見間違い(=読み間違い)かと思うほどまで、
自然と呆れてしまった。
(堀川天皇が)ご存命でいらっしゃった折より、このような仰せ[=白河上皇が
鳥羽天皇(当時は東宮)のもとに作者を出仕させるよう仰せになっていたこと]
があるとは聞いていたけれど、(その上皇の意向に対して)何とも(堀川天皇の)
ご返事がなかったのは、そうでなくても(=私が鳥羽天皇のもとに出仕しなくて
も)と、お思いになっていたのではあるまいか、それなのに、
イ いつしかといひ顔に参らんこと、あさましき。
周防の内侍(すほうのないし)《注…仕えていた後冷泉天皇が崩御すると家に
下がったが、後冷泉天皇の弟、後三条天皇の即位後、再び出仕した》が、
後冷泉院に先立たれ申し上げて後、後三条院から七月七日に参内せよ、という
仰せがあったときに、
天の川おなじ流れと聞きながらわたらんことはなほぞかなしき
【天の川の流れのように、後冷泉院も後三条院もご兄弟で、同じ血筋とは聞い
てはおりますが、天の川を渡るように、新しい天皇に引き続き出仕することは
やはり悲しいことです】
と詠んだとかいうことも、なるほど本当に(その通りだ)と思われる。
「故院《注…亡き堀川院》の御形見としては、
ウ ゆかしく思ひまゐらすれど、
(自分から出仕するような)差し出がましいことは、やはりあってよいことでは
ない。その当時(堀川天皇のもとにはじめて)出仕したときでさえ、(宮仕えの)
晴れ晴れしさは思い悩んだけれども、親たちや三位殿《注…弁の三位とは
別人。作者の姉で、やはり宮中に出仕している》などがしなさることなので、
と思って、(出仕を拒否する気持ちを)口に出せることでもなかったので、心の
中だけで海人の苅藻(かるも)のように思い乱れたのであった。
なるほど本当に、今回のことも(=鳥羽天皇への再出仕も)、我が意のままには
ならないと言ってしまいそうなことではあるけれど、また(あるいは)、(私が)
世を思い捨てて出家してしまったとお聞きになったならば、(白河上皇は)それ
程までには(私のことを)大事だとはお思いにならないだろう」と思い乱れて、
今少し、ここ数ヶ月より悩みが増すような心地がして、
「エ いかなるついでを取りいでん。
(しかし)そうは言ってもやはり、自らの(感情に任せて)髪をそぎ捨てるのも、
昔の物語にも、そのようにした人のことを、人々も『嫌な心であるよ』
[木山注…感情に任せた衝動的な出家は生(なま)悟りの出家として忌まれた]
などと言うようだが、私自身の心にも、本当にそのように思われることなの
で、さすがに本気で決心することも出来ない。
オ かやうにて心づから弱りゆけかし。
そうしたら、それにかこつけてでも(再出仕を断わることが出来よう)」と思い
続けられて、数日間過ごしていると、 「御乳母(めのと)たちは、まだ六位の位
で、五位にならないかぎりは、お食事を差し上げられないことです。[木山
注…天皇が召し上がる食事には五位以上の女が任じられた]この二十三日、
二十六日、二十八日が(出仕するのに)良き日です。早く、早く」と書いてある
文が、たびたび見えるけれど、決心する心地もしない。
「過ぎ去った年月でさえ、わたくしのもの思ひ《注…筆者の一身上の悩み》
の後は、人々の間に立ち交じる有様でもなく、見苦しく痩せ衰えてしまった
ので、どうしたらよいだろうかとばかり、自然と思い悩んだけれど、(堀川天皇
の)お心の親しみやすさに(出仕を続け)、人々のお心についても、三位《注…筆
者の姉の三位殿》がそのまま出仕を続けていらっしゃったので、その人たち
のお心に背くまい、などと(思って)、ちょっとしたことにつけても自然と心の
用意ばかり(=気を使ってばかり)して過ごしていたのに、今さらに(鳥羽天皇の
もとに)立ち出でて、以前見た世のように過ごすことも難しい。
[木山注…以前堀川天皇にお仕え申し上げた時のようにはお仕えすることも
出来ない の意]
君(=鳥羽天皇)は幼くていらっしゃる。そのように(私のことを父の堀川天皇の
もとで宮仕えに)慣れてしまった者だと、お思いになることもあるまい。
そのような状態のままでは、(私は)昔のことばかりが恋しくて、
カ うち見ん人は、よしとやはあらん」
などと思い続けるうちに、袖が絶え間なく涙で濡れてしまったので(次のような
歌を詠んだ)、
キ 乾くまもなき墨染めの袂(たもと)かなあはれ昔のかたみと思ふに
[設問]
以下、今年の添削通信の合格者(文科一類・文科三類)の再現答案を紹介しつつ、解説します。
(一) 傍線部ア・ウ・オを現代語訳せよ。
ア
Aさん⇒長年、宮仕えしなさるお気持ちのすばらしさ(若干減点か)
Bさん⇒あなたの長年宮仕えなさるお心遣いのめったにない程のすばらしさ(正解)
木山⇒長年、宮仕えなさっているお心がけの滅多にないほどの素晴らしさ。
*『年ごろ』直単A名41…長年・ここ数年間『ありがたし』B形9…滅多にない《滅多にない程すばらしいなどプラス評価のことが多い》
作者が長年典侍として堀河天皇に仕え、看病にも携わったことを踏まえて
” 長年の滅多にない程すばらしい宮仕えの御心 " と言っている訳ですから、
『御心』の訳出には少し工夫が必要です。
私の答案を含めて、諸解答はすべて『お心がけ』という語を用いていますが、これは「どのような事態にもいつでも対応できる心の準備」といったような意味で、帝に対する行き届いた配慮が求められる典侍の立場を良く表す言葉と言えます。Bさんが使った『心遣い』は「その人のためを思っていろいろと気を使い配慮すること」ですから、これも許容されると思います。しかし、Aさんの ” お気持ちのすばらしさ " では、行き届いた配慮・心構え・心遣いのニュアンスが出ず、若干減点されるのではないか、と思います。
ウ
Aさん⇒お会いしたいと思い申し上げるけれど(正解)
Bさん⇒見たいと思い申し上げるけれど(若干減点か)
木山⇒お目にかかりたく思い申し上げるけれども
別解⇒心引かれてお慕いしたく思い申し上げるけれども
*『ゆかし』C形79…見たい・聞きたい・知りたい(心引かれる)『〜まゐらす』公式54②謙譲の補助動詞…〜申し上げる。 “ 御院の御かたみ " とは、亡き堀河天皇がこの世に残した忘形見の幼帝鳥羽天皇のこと。その鳥羽帝に会ってみたい気持ちはあるけれど、という主旨ですが、『〜まゐらす』という謙譲の補助動詞が付いており、また、常識的にも典侍から見れば天皇は恐れ多く敬うべき対象ですから訳出にはその点の注意が必要です。 諸解答が河合塾以外は全て「お目にかかる」という語を用いているのは、それがお会いするという意の謙譲語であり、自分を低くすることで相手を敬う言い回しであるからです。河合塾の答案のみ『ゆかし』を「心引かれる」の方向で訳出しており、「慕わしく思い申し上げるけれども」としています。その方向の訳出もありだと思うので別解に示しました。Bさんの答案は微妙です。確かに謙譲の補助動詞の訳出は付いていますが、天皇に対して『見たい』という直截な表現で切り出すのはどうか、ちょっと不敬ではないか、といった疑念は残ります。結局、採点官の裁量というところでしょうか?
オ
Aさん⇒出家を迷ううちに心から弱っていってしまえよ (ほぼ正解だが若干減点か)
Bさん⇒このようにして心が自分から弱りゆけよ(ほぼ正解だが若干減点か)
木山⇒このように自分の心のままに自然と弱っていけよ。
別解⇒このように思い乱れたまま自然と衰弱していけよ。
*末尾の『〜かし』はE他11…《念推しの終助詞》〜よ。 例えば “ 歌詠ませたまへかし " は、「歌をお詠みなさいませ・よ」などと訳します。ポイントは頻出単語ではない『心づから』をどう訳上に反映させるかです。接尾語の『〜づから』は、名詞について「〜のままに」の意を表し、これが例えば、己(おのれ)を表す「己(おの)」に付けば『おのづから…自分から/自然に』となり、「手」に付けば『手づから…自分自身の手で/わざわざ自分自身で』などとなります。 今回のように「心」についた場合は、『心づから…心のままに自発的に/心のままに自然に』などと解釈するのがふつうです。 つまり、直訳は ”このような状態で自分の心のままに自然と私の身体が弱ってゆけよ/弱って行けばよい " となります。 Aさんの「心から〜」Bさんの「自分から〜」は、『心づから』の持つ「自然に/自発的に(ソウナッテシマエバヨイ)」のニュアンスを充分には表しておらず、若干減点されるのではないか、と思います。 別解は「かやうにて」の部分を指示語の戻しと見て、『このように思い乱れた心のままに自然と〜』とした答案例です。諸解答では代ゼミのみが、このような指示語を戻した解答を紹介していましたが、前後の文脈から自明のような気もしますし、絶対の要件ではないと思います。
(二) 「いつしかといひ顔に参らんこと、あさましき」(傍線部イ)とはどういうことか、説明せよ。
Aさん⇒新天皇の所への出仕を待ちわびていた様子で参上するのは呆れたことだということ。(正解)
Bさん⇒作者は堀河天皇の喪に服しているのに早くも再び出仕することは驚きあきれたことで出来ない。(←「いつしかと言ひ顔」の訳出がない点で減点)
Cさん⇒すぐにでも出仕したいという顔でお仕えするのは、あきれたことで出来ないということ。(正解)
木山⇒いかにも早く出仕したがっているかのような顔で再出仕するのは、呆れたことで出来ないということ。
*『いつしか』公式39…はやく〜(たい)。妖怪人間ベム・ベラ・ベロ ” いつしか人間にならばや!⇒はやく人間になりたい!" と覚えましたが、時代が変わって今の学生さんは知らないかも。『〜顔』は多く「〜がお」の形で、動詞の連用形などに付いて、そのような様子/表情であることの意を表します。例えば「したりがほ」「人待ちがほ」「心得がほ」など。
『あさまし』はB形2…驚きあきれるの意。Aさん、Cさんは正答しています。Bさんは『〜といひ顔に』の訳出「アタカモ〜な様子で/〜な表情で」の訳出が欠落しているので、その点で減点されるだろうと思います。
(三) 「いかなるついでを取り出でん」(傍線部エ)とはどういうことか、言葉を補って説明せよ。
Aさん⇒どのような出家の理由を用意したら良いのかということ。(正解)
Bさん⇒ 再び出仕するのにどのようなつてを取ろうかということ(不正解)
Cさん⇒筆者がどのような口実で出仕を断ろうか悩んでいるということ。(不正解)
木山⇒再出仕を逃れるため、どのような機会に出家を遂げようか、ということ。
*「ついで」には①(物事の)順序・順番、②機会・折の二つの意がありますが、ここは“ 出家の機会 "ととるのが正しい解釈です。作者は再出仕を回避する為に、「どのような出家の機会を見つけて出家を成し遂げようか」と思いを巡らしますが、しかし、その直後には『さすがに(=そうは言ってもやはり)、われと削(そ)ぎすてんも、〜〜〜人もうとましの心やなどこそいふめれ。』と逡巡しています。
古文背景知識No.1でも詳しく解説しているように、仏教が最も嫌うのは俗世に対する執着心です。そうした俗世への未練・こだわり・執心を心に残したまま形だけ出家してしまうことは、“ 最も心汚いこと " として人々に忌まれました。
そもそも『感情に任せて衝動的に出家する』という表現自体が矛盾を含んだ表現といえます。出家とは、世の無常を心底悟り、俗世への執着を断った者が為す行為であって、感情に任せて衝動的にするものではありません。例えば、男に振られた女の人が、相手の男への当てつけに衝動的に髪を切ったような場合、それは形の上では出家と言えますが、内面の心理としては大いに俗世への(=相手の男への)執着にとらわれた結果である、とも言えます。
作者の場合は、再出仕回避の為に、便宜的に出家を利用しようという訳ですから、やはりそれも本当には悟っていない生(なま)悟りの出家として世間の批判に晒されることになるでしょう。院の仰せがあった後に、慌てて出家した、ということであればなおさらです。
Bさん、Cさんが共に的外れな答案を書いてしまったことは、私には意外な感じがしました。古文背景知識No.1の音声解説を聴けば、生(なま)悟りの衝動的出家が忌まれることは説明していますし、添削通信の際にも数回チェックを入れているのですが、なぜ正答出来なかったのか不思議です。
直後の「さすがに、われと削ぎすてんも〜」以下の、作者の逡巡(しゅんじゅん)の文脈が読み取れなかったのでしょうか?
学生さんの中には「削ぎ捨つ」の意味が理解出来ない人も稀にいますが、当時の剃髪はハサミでジョキジョキ断髪するのではなく、剃刀を斜めに当てて髪を削ぎ切りに切り落とすやり方でした。
Aさんの答案は「ついで」を『(出家の)理由』と訳出している点が特徴ですが、本来「ついで」に理由という意味はありません。これは一種の意訳として “ どのような機会をとらえて(それを)出家の理由としたらよいか " といったニュアンスを表そうとしたものと思われます。「ついで」の意を出さずに、“ 理由 " とだけ書いてしまうのは、やや、微妙なラインですが、駿台の解答にも「機会」という語を用いず、『どのような出家の口実を見出したらよいか〜』という答案例があるので、“ (機会をとらえた)出家の口実/理由 " という意訳も許容される可能性がある、と判断しました。
(四) 「うち見ん人はよしとやはあらん」(傍線部カ)とあるが、なぜ「うち見ん人」は良いとは思わないのか、説明せよ。
Aさん⇒堀河天皇のいた昔ばかり恋しく思って幼い新天皇に親身に仕えないのは無責任だから。(正解)
Bさん⇒鳥羽天皇は幼くて作者に慣れ親しんでもおらず、作者も堀河天皇のことばかりを恋しく思っているから(やや減点)
木山⇒作者が故院ばかりを恋しがっていては、新帝には相応しくないと傍目には映るから。
*前後の文脈を整理してみましょう。作者は、「御心のなつかしさに」《=堀河天皇のお心の親しみやすさに》出仕を続けてきたのに、「いまさら立ち出でて、見し世のやうにあらんこともかたし」《=以前、堀河天皇にお仕えしていた時のようにはお仕えすることも難しい》、「さらんままには昔のみ恋しく」《=そのような状態のままでは、昔の堀河天皇のことばかりが恋しくて⇒そんな状態で再出仕すれば、「うち見ん人はよしとやはあらん」《=傍目に見る人の目には、そのような私の状態をまぁまぁよいとでも見るだろうか、いや、そうではあるまい》といった文脈です。
つまり、亡き堀河天皇のことばかりを恋しがっている作者では、新帝に親身にお仕えしているとは見なされず、新帝に相応しいものではないといった批判が、周りの視線を通して起こってくるに違いない、と作者自身が考えている、ということです。
Bさんの答案中の “ 鳥羽天皇は幼くて作者に慣れ親しんでおらず " は不適切で減点されます。「君はいはけなくておはします。さてならひにしものぞとおぼしめすこともあらじ」《=現代語訳参照》は、作者の側からの推察であり、確定した事実ではありません。そもそも作者と新帝はまだ会ったこともないのですから、新帝が作者に慣れ親しまないという事実が先にあるわけでもなく、従って、それを再出仕拒絶の理由にするのもおかしな話になります。
(五) 「乾く間もなき墨染めの袂かなあはれ昔のかたみと思ふに」(傍線部キ)の和歌の大意を説明せよ。
Aさん⇒堀河天皇の形見だと思うと涙で喪服が濡れ続けている(正解)
Bさん⇒堀河天皇を思い涙で濡れる喪服を、堀河天皇の形見と思う(正解)
Cさん⇒鳥羽天皇が亡き堀河天皇の形見だと思うと、物悲しく涙が止まらない。(不正解)
木山⇒故院を偲ぶ形見でもある喪服の袖が、乾く間も無く涙で濡れているということ。
*『墨染め(衣)』直単D基26…喪服。「乾く間もなき⇒袂(たもと)」…乾く間もなく流れる涙。
Cさんが “ 墨染め = 喪服 " の訳出をせずに、形見の対象を「喪服」ではなく、堀河天皇の「忘れ形見の鳥羽天皇」と見たのは、全体の趣旨が全く違ったものになりますから、部分点なしの失点となります。堀河天皇の忘れ形見の幼帝鳥羽天皇の姿を見て作者が涙する、というシュチュエーションは実際に鳥羽天皇の姿を目の当たりにした時に生じる感慨であって、再出仕もしていない《従って鳥羽天皇に会ったこともない》この状態でその解釈をとるのは無理があります。あくまで、この状況で「形見」の対象として作者が見ているものは、「墨染めの袂」と考えるべきです。


第三問〔漢文〕
次の文章を読んで、後の設問に答えよ。
[書き下し文]
凡(およ)そ
a 著 シレ 書ヲ 立ツルハレ 論ヲ、 必ズ 本(もと)ヅク二 於
不シテレ 得レ 已ムヲ 而 有ルニ一レ 言。
《書を著(あらは)し論を立つるは、必ず已(や)むを得ずして言(げん)有るに
本(もと)づく。》
而(しか)る後に言(げん)当(あ)たり、其(そ)の言(げん)信(まこと)にして、
其の言(げん)用(よう)有り。
故(ゆえ)に君子の言、事理(じり)に達して止(や)み、敷衍流宕[注…ふえん
りゅうとう/節度なく述べ立てること]放言高論(ほうげんこうとう)し、
b 取ルヲ中 快ヲ 一 時二上。
為(な)さず。
蓋(けだ)し要(よう)に非(あら)ざれば則ち厭(いと)ふべく、確(かく)ならざれ
ば則ち疑ふべし。
既(すで)に厭(いと)ひ且(か)つ疑へば、其の書貴(たふと)び信ずべからず。
君子の言は、
c 寒 暑 昼 夜、
布帛菽粟(ふはくしゅくぞく)[注…布と絹、マメとアワ、日常の衣服や食べ物
を指す]のごとく、疑ふべき無く、厭ふべき無し。 天下万世(てんかばんせい)
信じて之を用(もち)い、
d 丘 山 之 利、
有りて、豪末(ごうまつ)の損(そん)無し。
此(こ)れを以(もっ)て古今(ここん)の作者を観(み)れば、昭然(しょうぜん)
として、白黒のごとし。
書を著(あらは)すに諸(こ)れを身(み)に本(もと)づけざれば、則ち只(た)だ
是(こ)れ其の言を鬻(ひさ)ぐ[注…売ること]者なるのみ。
老荘(ろうそう)申韓(しんかん)[注…老子・荘子(道家)、申韓(法家)の略]の
徒(と)、学術
e 雖モレ 偏ナリト、
要(よう)は各(おのおの)能(よ)く自(みづか)ら天下後世(こうせい)に
見(あらは)る。
斯(こ)の義や、古(いにしへ)の文章の士は猶(な)ほ能(よ)く之に及ぶ。
降(くだ)りて能(よ)くせずして乃(すなは)ち剽賊(ひょうぞく)[注…剽窃。
賊は、ぬすむ]せり。
夫(そ)れ剽賊して以(もっ)て文を為(つく)るすら、且(か)つ以て後(のち)に
伝ふるに足らず、而(しか)るに況(いは)んや剽賊して以て書を著(あらは)す
をや。
然(しか)り而(しか)うして
f 有ルレ 識 者 恒(つね)二 病ム二 書 之 多キヲ一 也、
豈二 不ランヤレ 由ラレ 此二 也 哉。
《識者恒(つね)に書の多きを病(や)むなり、豈(あ)に此(こ)れに由(よ)
らざらんや。》
(方東樹『書林揚觶(ようし)』による)
[現代語訳]
およそ(一般的に)
a 著 シレ 書ヲ 立ツルハレ 論ヲ、 必ズ 本(もと)ヅク二 於
不シテレ 得レ 已ムヲ 而 有ルニ一レ 言。
《書を著(あらは)し論を立つるは、必ず已(や)むを得ずして言(げん)有るに
本(もと)づく。》
そうやって後に(はじめて)、その言葉は妥当であり、その言葉は誠(まこと)であって、その言葉は有用である。
ゆえに、君子の言葉はものごとの理(ことわり)に達してやめており《つまり、真理に到達した上で論を終えており》、節度なく述べ立てたり、好き勝手に言い放ったり、高ぶった議論をしたりして、
b 取ルヲ中 快ヲ 一 時二上。
ことなどしない。
思うに、重要でないのならば、すなわち嫌うべきであり、(根拠が)確かでないのならば、すなわち疑うべきである。すでに嫌って且(か)つ疑っていれば、その書物は尊んで信じることなど出来ない。
君子の言葉は、
c 寒 暑 昼 夜、
日常の衣服や、日常の食べ物のように(ごく当たり前に受け入れられて)、誰も疑うべきものが無く、嫌うべきものも無い。《木山注…君子の言葉は、季節の変化による寒暑や、昼夜の運行や、日常生活の衣食のように、ごく当たり前に受け入れられていて、誰も疑ったり嫌ったりしないほどに普遍的に信じられているものだ、の意》
天下の万世は信じてこれ(=君子の言葉)を用いて、
d 丘 山 之 利、
が有って、ほんのわずかの損害もない(=ほんのわずかの損害を被ることもない)。
このことをもって、昔と今の作者(=文筆家)を観察してみると、明らかなさまとして、(その違いは)白と黒のようである(=白と黒のようにはっきりと異なっている)。
書物を著すのに、これを自分自身(の考え)に基づかなければ、すなわち、ただその言葉(=他者の言葉)を(借用して)売っている者にすぎない。
道教や法家の学徒は、その学問は
e 雖モレ 偏ナリト、
要は(結局は)、おのおのよく自分で天下や後世までも(文章を残して)現れているのである。
この意については、昔の文筆家はなおよくこれ(=後世の学問)まで及んでいるのである。(しかし時代が)下って、(今では)それがよく出来なくなって、他人の文章を剽窃している(盗用している)。
そもそも、剽窃して、それでもって文章を作るのでさえ、後世に伝えるには値しない(価値がない)。それなのに、まして剽窃して、それでもって(一冊の)書物を著(あらわ)すのなら、なおさら伝える価値がない。
そういうわけで、
f 有ルレ 識 者 恒(つね)二 病ム二 書 之 多キヲ一 也、
豈二 不ランヤレ 由ラレ 此二 也 哉。
《識有る者恒(つね)に書の多きを病(や)むなり、豈(あ)に此(こ)れに由(よ)
らざらんや。》
《木山注…知識ある者は、つねに書物が多いことを気に病んでいる。その理由はまさに『このこと』に依(よ)るのである。⇒多くの書物があることは、粗悪な模倣や剽窃を伴うので、むしろ憂慮すべきである、の意。つまり、『このこと』とは、近年の著作者が後世に伝える価値のない剽窃の書物や文を多く著している現状を指す》
[設問]
(一) 傍線部b・d・eを平易な現代語に訳せ。
b
Aさん⇒ 愉悦を一度に得ることを(不正解)
Bさん⇒一時的に快楽を得ることを(正解)
木山⇒一時的に満足を得ること/一時的に快楽を得ること
*節度もなく、無責任な、好き勝手な、高ぶった放言をして⇒『快を一時(いちじ)に取る』といった文脈ですから、“ 好き勝手に言い放つことで一時的な快楽/愉悦を得る " と解釈するのが最も自然です。つまり『一時(いちじ)に』を「一時的に」と取るのが正解です。
Aさんの答案の「一度(いちど)に」は、同時に物事が集中するさまを表し、同様の表現には「いっぺんに/一挙に/一気に/一息(ひといき)に」などがありますが、本問の場合、“ 一挙に・一気に快楽を得る " という意味にならないことは明白だと思います。好き勝手な言い放ちの持つ軽薄さを表すために、結局、それは一時的な快楽に過ぎない、と言っているわけで、“ そうすることで快楽を一気に得ている " 訳ではありません。
d
Aさん⇒たくさんの利益(正解)
Bさん⇒すばらしく高い利益(やや減点)
木山⇒丘や山のような大きな利益
*Bさんの答案の「高い利益」という表現には少し違和感を感じます。利率を言う時などは “ 高い利率/利益率 " などと言いますが、利益そのものを修飾する時に「高い利益」とは言わないのでないでしょうか。
e
Aさん⇒偏っているとはいえ(正解)
Bさん⇒かたよっているけれど(正解)
木山⇒偏りがあるとはいえ
*漢単A43『偏…かたよル・かたよリ』公式4③『〜ト雖(いへど)モ…逆接』
(二) 「著レ書立レ論、必本二於不レ得レ已而有一レ言」(傍線部a)とはどういうことか、簡潔に説明せよ。
Aさん⇒書物を書き、立論するには必ずどうしても言葉を用いる必要があるということ。(不正解)
Bさん⇒書物を著し自論を述べるには、必ずどうしても仕方なく存在する意見に依拠するということ。(不正解)
Cさん⇒書物を著し、理論を立てることは、必ず言語によらざるを得ないということ。(不正解)
木山⇒どうしても言わざるを得ない言葉があればこそ、書を著し自説を展開したりするのだということ。
別解⇒止むに止まれぬ言葉に基いてこそ、著作や立論はなされるのだということ。
*この場合の『已(や)むを得ずして』は、已(や)むに已(や)まれぬ(止むに止まれぬ)…止めようとしても止められない/そうしないではいられない、の意で用いられており、傍線部の直訳は、「(およそ一般的に)書物を著(あらわ)し、論を立てて展開するには、そうしないないではいられないような言《=自説》が有るということに基づくものだ」となります。
つまり、抑え切れないほどの内的衝動としての自説への強いこだわりがあってこそ著作をなしたり、自論を立てて論ずることが出来るのだ、という意味です。
この解釈は、傍線部以下の文脈、「そうであって後にはじめて、その言葉は妥当であり、その言葉は誠(まこと)であって、その言葉は有用である」とも上手く繋がります。
一方、Bさんのように「已むを得ず」を ” 仕方がない/どうしようもない " といったネガティブな方向で解釈しても前後の文意が上手く整合しません。
また、Aさん・Cさんのように『立論は言葉や言語に依る』というのでは、当たり前すぎて ”言わずもがな " な感じになってしまいます。
止むに止まれぬ言説への衝動が著作・立論の原動力になる、という主張は、私には理解しやすいように感じられますが、残念ながら今回の3名の方はいずれも不正解となりました。
ところで、代々木ゼミナールの解答速報に、『書物を著し議論を立てる場合、重要で確実な必要最低限の言葉だけを用いるべきだということ。』とあり、「已を得ず」を ” 仕方なく取らざるを得ない必要最小限の言葉 " と解釈した点で、誤答の可能性が高いと思います。
(三) 「寒暑昼夜」(傍線部c)は「君子之言」のどのようなありかたをたとえているか、簡潔に説明せよ。
Aさん⇒いついかなる時でも重要で確かなものであるというありかた。(ほぼ正解だが)
Bさん⇒君子の言は疑われることなく至極当然なこととして存在する有り様。(正解)
Cさん⇒日常の事象のように、明白で疑問の余地がないありかた。 (正解)
木山⇒当たり前に受け入れられていて嫌疑の余地なく信奉されている在り方。
別解⇒季節や時間の流れのように、誰もが疑いなく受け入れられる在り方。
*傍線部の前後を繋げば、「君子の言は〜日常の衣服や日常の食べ物の如く、疑うべき無く、厭(いと)うべき無し」となりますから、その間に入る『寒暑昼夜』も ” 誰もが日常の衣服や食べ物のように何の疑念もなく、好悪を越えて当たり前に受け入れているもの "といった方向で考えることになります。
そう考えれば、確かに季節の変化による寒暑や、昼夜の運行は、何の疑念もない当たり前のこととして受け入れられていますから、前後の文脈にも整合します。例えば、君子の言として『光陰矢の如し』という格言があったとして、それを聞く人は実にその通りだなぁと、疑いもなく、しみじみとその言葉の真実性を実感するわけです。別な言い方をすれば、君子の言というものは、人々にとって何の嫌疑の余地もなく受け入れられる、ある種の普遍性を備えた言説である、とも言えます。《駿台の解答には『〜普遍的なあり方』というフレーズが使われています》
Aさんの答案の「いついかなる時にも〜確かなもの」という表現は、疑念なく受け入れられていることの逆向きの表現として許容されるかも知れませんが、やや危うく、やはり ” 疑念なく受け入れられ " という語句を用いた方が安全です。また、寒暑昼夜の運行は自明なものとして受け入れられている、というニュアンスですから、それが『重要で』あると認識されている訳ではない、と思います。
(四) 「有レ識者恒病二書之多一也、豈不レ由レ此也哉」(傍線部f)とあるが、「此」は何をさしているか、わかりやすく説明せよ。
Aさん⇒他者の言葉を盗用して、後世に伝える価値のない書物が無尽蔵に作られているということ。(正解)
Bさん⇒古人の賢人の作った文章を十分理解せずに盗用し文章を作るのは無価値で、著された書物など後世に伝える価値が全くないという考え。(末尾の考えは減点)
Cさん⇒剽窃によって、後世に残すに値しない書物が増えているということ。(正解)
木山⇒近年の著作者が、後世に伝える価値のない剽窃の書物や文章を多く著していること。
*[現代語訳]の傍線部fの下の木山注の説明をお読み下さい。『此れ』が指すものは、近年の著述をめぐる現状そのものですから、観念的な考え方を指している訳ではなく、その点でBさんの答案末尾の「〜という考え」という部分は減点されます。