お便りシリーズNo.82
= 令和7年・2025年
東京大学古典だより(古文漢文) =

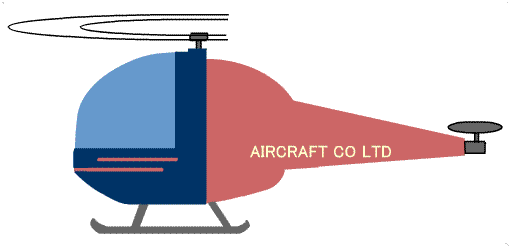
増賀上人・アシシの聖フランチェスコ
陰徳聖と呼ばれる人びとの奇行
武芸者も真の奥義に到達してしまうと、もう剣などは握らなくなり、道の真ん中に暴れ馬がつながれていれば、別の道を廻って「君子危うきに近寄らず」これぞ武芸の奥義じゃ、という悟道(ごどう)に達してその道の教祖のようなものとなります。
弓を捨てた弓の名人や剣を捨てた剣の名人のもとに教えを請いに行っても、剣術や弓術はどこかへ霧散して、彼はすでに奥義を極めたやんごとなき教祖となっているので、常人には理解し難い、時にはアホのような言葉、しかしながら心酔する者にとっては悟道のこもった深淵な一句を与えては、人々を深く感服せしめたりするわけです。
仏教の理念は、かりそめの仮象の現世への一切の執着を断つことであり、捨ててこそ仏の道、ということであれば、その仏教への執着も捨ててしまおうという究極の仏道者もやがて現れ、狂人めいた奇行の僧となりますが、それも見る目をもった者が見れば、悟りを極めた悟者(ごしゃ)と映ります。
こうした破戒僧(はかいそう)が、たまたま「あ・・」とつぶやけば、これは阿含(あごん)経の根本原理を示唆されたのだ と忖度(そんたく)し、たまたま「う・・」とつぶやけば、おぉ、今おっしゃった「う」とは、宇宙須弥山(しゅみせん)世界の根本を示されたのだ、あぁ、何と尊いことか!と感涙にむせんだりします。
踊り念仏を広めた時宗(じしゅう)の一遍(いっぺん)は捨聖(すてひじり)と呼ばれ、最後には自身の宗門さえも捨て去り、死後に宗門を立てることを意図しなかったがゆえに、一遍の死後、時宗は自然消滅とあいなったのですが、これもまた、宗門一同、見事なまでの ” 捨てっぷり " というべきです。
中世という時代は洋の東西を問わず、捨てまくる人々が現れる時代で、かの有名なアシシの聖フランチェスコは、父親の家業の商売に背を向けて自分の道を進もうとし、着ていた服を全部脱いで素っ裸となり、「全てをお返しします」と父に差し出し、人の親の父を父とせず、天の父のみを父とすると言い放って親子の縁を切ったのでした。
素っ裸になる点では、我が日本の道心者も負けてはいません。平安中期の増賀上人(ぞうがしょうにん)は、
『あるとき、ただ一人伊勢大神宮に詣でて祈請(きせい)し給ひけるに、夢に見給ふやう、道心おこさむと思はば、この身を身とな思ひそと、示現(じげん)を蒙(こおむ)り給ひける。うち驚きておぼすやう、名利(みょうり…現世での名誉や利益)を捨てよとこそ侍るなれ。さらば捨てよとて、着給ひける小袖衣(こそでごろも)、みな乞食どもに脱ぎくれて、ひとへなる物をだにも身にかけ給はず、あか裸にて下向し給ひける。見る人、不思議の思ひをなして、「物に狂ふにこそ。見め様などの、いみじきに、うたてや」など言いつつ、うちかこみて見侍れども、つゆ心もはたらき侍らざりけり』〔撰集抄〕
という潔(いさぎよ)さ。
そのまま伊勢から比叡山まで素っ裸のまま歩いて帰ります。
師であった比叡山中興の祖、慈恵僧正(じえそうじょう)が、余りのことなので前ぐらいは隠して『威儀を正しくして、名利(みょうり)をはなれ給へかし』と諌(いさ)めるけれど、増賀は聞く耳を持たず、「名利をながく捨て果てむ後には、さにこそ侍るべけれ。あら楽しの身や、をうをう」と叫びつつ比叡山の山門を出奔して、そのまま大和の国の多武峰(とうのみね)に籠ります。
中国の禅宗の第一祖はインドからの渡来僧の達磨(ダルマー)、この人が興したお寺が少林寺、壁に向かって9年間座禅をし続けます。そこへのちに第二祖となる中国人の慧可(えか)が入門を求めてやって来ます。
『師よ、我が心(こころ)安んぜず、請(こ)ふ、我が心を安んぜしめよ』
《=先生、私の心は安らかではありません。どうか安らかにして下さい》
達磨曰(いは)く、
『汝が心を来らしめよ、汝がために安んぜん』
《=お前さんの心とやらを持って来い、そうすれば安らかにしてあげよう》
慧可はしばらく考えますが、どう答えて良いか分からず、
『心を求むれど心は不可得(ふかとく)なり』
《=自らの心を探し求めるとは言っても、これといって差し出せるものではありません》と答えます。
すると達磨は静かに言いました。
『汝が心を安んじおはんぬ』
《お前さんの心を安らかにしてあげたよ》
オワリ。
さらに言えば、大乗仏教においては人間の自我もまた空なりという立場です。
人間の心=自我というものは果たしてあるのでしょうか? 心を持って来いと言われても、差し出せる心という実体があるわけでもありません。つまり、達磨の答は、『慧可よ、ありもしないもので悩むな!無いもので悩むな!人間の自我もまた空なのだ!』です。
結局、人間の自我は一瞬一瞬に移り変わっていく川の流れのようなものにすぎません。” あの事だけは絶対に許せない " という流木が流れて来たら、それに囚(とら)われるから苦しくなるわけで、ただ黙って流れ去っていくのを待てば良い、というのが達磨の教えです。これを安心問答(あんじんもんどう)と言います。
衣服を捨てる、宗門を捨てる、大寺院の宗教的地位を捨てるどころではありません。道心者の究極の ” 捨てっぷり " は最終的に、自らの自我をも捨てる(=自我にこだわらない)、という境地にまで行き着きます。
《平安時代半ば、醍醐天皇の皇子ながら寵愛を受けられず、都を出奔して市井(しせい)に生きる聖(ひじり)となった空也(くうや)上人は、諸国を放浪しながら、ひたすら「欲も恨みもすべて捨てよ」と説き続けました》
では、自我をも捨て去った人の心はどうなるのでしょうか?空の概念はニヒリズム(虚無主義)ではありませんから、絶望や虚しさに至るわけではありません。ここがブッディズム(仏教)の面白いところですが、自我も含めて全ての執着を捨て切った人の心は、むしろ逆に、自由で安らかな喜びに満ちる、というのが仏教の立場です。
この空の境地を礼讃(らいさん)したお経が、あの有名な『観自在菩薩 行深般若波羅蜜多(かんじんざいぼさつぎょうじんはんにゃはらみた)で始まる「般若心経(はんにゃしんぎょう)」です。おそらく日本のお経の中で一番有名なお経であり、お遍路さんが唱えたり、写経したりするのはだいたいこのお経です。わずか266文字の短いお経ですが、仏教徒でなくても、そこに書かれた透徹な認識論には深遠な印象を受けるのではないかと思います。私の勝手な抄訳で紹介すればこんな感じです。
![]()
シャーリプトラよ、あらゆる存在に実体はないのだ。
これを名付ければ「空(くう)」である。
また、あらゆる存在は変化を繰り返す。これを名付ければ「無常」である。
存在には「変化」があるだけで、生まれもしなければ死にもせず、増えもしなければ減りもしない。
「自分」という存在もまた空である。だから自我にとらわれるな。
あらゆるものは有るようで無いのだ。
存在の真実を見抜きなさい。
この存在の真理を深く悟る者だけが、自由で心安らかでいられる。
世界と自分を隔てていた虚構が崩れ去る認識は、なんとすがすがしいことか!
しかし、その真理を知ろうとせず、不変を求め、不変なるものが存在すると錯覚するところに人間の苦が生じるのだ。
![]()
般若心経は、一切の存在が空であるという仏教の根本的な教えを説いています。それは、物事の執着を手放し、心の平安を得るための教えです。
では、出家して高僧や聖(ひじり)と呼ばれるようになり、人々の尊崇の対象となった者の名利(みょうり)はどうなるのでしょうか。それもまた名声や名誉といった俗世の名利を引き寄せることにならないでしょうか?そのような名利はどうやって捨てたらよいのでしょうか?
その点については、私のホームページ上に載せている 『古文背景知識No.12』に関連する内容が書かれていますので、以下に引用します。併せて、「陰徳聖(いんとくひじり)説話」の出題パターンも学んで下さい。
*空の概念は一切の名利みょうり(栄達や誉れ)・名聞みょうもん(世間の評判)から離れることを要求しますが、そのような名利・名聞を捨てて、徳高い僧となり人々の尊崇の対象となってしまうことが、また一方では名利・名聞になってしまう、という矛盾に陥ってしまいます。
真の仏道者は、そのような名利・名聞の中に安穏としているわけにはいきませんから、そういう名利でさえも捨てなければなりません。
じゃあどうするのかというと、あえて狂気を演じ、不浄の中に身を置くいっかいの乞食僧の姿で俗世の底辺に生きていくとか、またはあえて僧侶が守るべき戒(かい)をやぶる破戒僧(はかいそう)のふりをしてまでも、名利への執着を捨て切ろうとするわけです。
このような人々のことを一般に隠徳僧(いんとくそう)または隠徳聖(いんとくひじり)といいます。平成3年センター追試『閑居の友』には、そうした隠徳聖の話が紹介されています。
ですから、一般に仏教説話で、とんでもない乞食僧や奇行の僧の話が始まったら、実は結末では隠徳聖であることが露見し、人々が彼の生き方に感動した、という展開になるのではないか、という見通しを持って読んで差し支えないと思います。(隠徳だと思っていたのに、正真正銘のバカだったという話はありません。)
ところで、隠徳聖の話というのは、逆に言えば、隠徳に失敗した僧の話、つまりバカな乞食と同じように見えて、ひょっとした拍子に実は徳高い尊い僧なのではないか、と思わせる行動をとってしまうお話です。
それはたとえば、天台宗の難解な教理を見事に解き明かすとか、世の無常めいた言葉をさらりと言ってのけるとか、最後は西方浄土のある西に向かって死んだとか、死に際に紫雲たなびいて仏の来迎があったとか、そんなふうな結末になっていて、それに対する説話作者の感動が述べられます。
平成3年のセンター追試の問5の解答は、「乞食の生涯に徹し、仏道のことさえ何も知らないようなふりをしたところに、恩愛の情や名誉欲までも捨て去った真実の仏道修行者の姿を見出して、きっと極楽往生を遂げたとこであろうと考えている」となっていますが、これなどは隠徳の概念がわかっていれば、すぐにパターン化されますから、簡単に即答できると思います。


第ニ問〔古文〕
この文章は『撰集抄』の一話である。これを読んで、後の設問に答えよ。
昔、御室戸(みむろと)《注…京都府宇治市の御室戸寺》の法印隆明といふ、
やんごとなき智者、もろこしに渡り給はんとて、西の国におもむきて、
播磨(はりま)の明石といふ所になん住みていまそかりけるに、
(ア) あさましくやつれたる
僧の、来たりて物を乞ふ待り。
さながら赤裸(あかはだか)にて、ゑのこ《注…子犬》を脇に抱き侍り。
人、後先(しりさき)に立ちて、笑ひなぶりける。あやしの者やと思(おぼ)して
見給へば、清水寺(きよみづでら)の宝日上人にていまそかりける。
(イ) ひが目にや
とよく見給へど、さながらまがふべくもあらざりければ
(ウ) かきくらさるる心地
して、伏しまろびて、「あれはめづらかなるわざかな」とのたまはせければ、
上人ほほゑみて、「まことに物に狂ひ侍るなり」とて、走り出で給ふめるを、
人あまたして、取りとどめ奉らんとし待りけれども、さばかり木暗(こぐら)き
繋みが中に入り給ひぬれば、
(エ) 力なくやみ侍りけり。
隆明法印は、あまりすべき方なく悲しく覚え給ひて、その事となく、その里に
とまり居給ひて、広く尋ねいまそかりけれども、その後はまたも見えずなり給
ひにき。さて里の者にくはしく事の有様を問ひ給へりければ、「いづくの者
とも人に知られで、この村に住みても二十日ばかりなり」とぞ答へ待りける。
(オ) この事、限りなくあはれに覚え待り。
何と、げに世を捨つといふめれど、身のあるほどは、着物をば捨てずこそ待る
に、あはれにもかしこくも覚えるかな。
およそ、この上人はよろづ物狂はしき様をなんし給へりけるなり。ある時は、
清水の滝の下に寄りて、合子(がうし)《注…ふた付きの容器》といふ物に水を
受けて、隠れ所をなん洗ひ給ふこと、常の態(わざ)なり。いみじく静かに思ひ
澄まし給ふ時も待るめり。
一方(ひとかた)ならず見給ひし。澄み渡る心の内は、いつも同じさきら
《注…才知》なれども、外(ほか)の振る舞ひは百(もも)に変はりけるは、
(カ) よしなき人の思ひを、我のみ一方にはとどめじ
と思しけるにや。
この上人ぞかし、中(なか)の関白《注…藤原道隆》の御忌に、
法興院《注…道隆の父兼家の別邸を寺としたもの》に籠(こも)りて、
暁方(あかつきがた)に千鳥の鳴くを聞き給ひて、
(キ)明けぬなり賀茂の河原に千鳥鳴く今日もはかなく暮れんとぞする
と詠みて、『拾遺集』《注…三番目の勅撰和歌集》に入り給へり。
明けぬるよりはかなく暮れぬべき事の、かねて思はれ給へりけるにこそ。
かの『拾遺集』には円松法印と載りて侍るは、上人の事にこそ。
現代語訳
むかし、東大御室戸寺の法印隆明という、尊い高僧が、「中国に渡ろう」と
思いなさって、西の国に向かい、播磨の明石という所に滞在していらっしゃる
時に、
(ア) あさましくやつれたる
僧で、やって来て物乞いをする僧がおります。まったく裸同然の姿で、子犬を
脇に抱えています。周りの人々は、前後に立って、笑ったり冷やかしたりし
た。(隆明は)「不審な者か」とお思いになってご覧になると、(なんと)
清水寺の宝日上人でいらっしゃったのだ。
(イ) ひが目にや
とよく(目を凝らして)
ご覧になるけれども、まさしく見間違うはずもなく(宝日上人)その人だった
ので、(隆明は)
(ウ) かきくらさるる心地
がして、(その場に) 倒れ伏して、「これは滅多にない事態であることよ」と
仰ったところ、上人は笑って、「本当に気が狂っておるのです」と仰って、
走り出ていらっしゃるように見えるのを、大勢の人を(隆明が)使って、引き
留め申し上げようとしますけれども、(上人は)木々がとても生い茂る中に
お入りになってしまったので、
(エ) 力なくやみ侍りけり。
隆明法印は、甚だしくどうしようもなく悲しく感じなさって、(他に)これと
いう理由や目的もなく、その里に留まりなさって、(上人の行方を)広く捜し
求めますけれども、その後は二度と(上人は)見られなさらなかった。
そこで(隆明)は里の者に詳しく事情を尋ねなさったところ、「どこの者とも
人々に知られないで、この村に住み始めて二十日ほどです」という回答でござ
いました。
(オ) この事、限りなくあはれに覚え待り。
何とまあ、確かに(出家は)「世を捨てる」と表現しますけれども、(そうは
いってもやはり)生きているうちは、(せめて)衣服は捨てないものでござい
ますのに、(衣服まで捨てなさった上人は)しみじみと心動かされ、立派にも
思われますなあ。
おおかた、この上人は、様々な正気を失ったような(常識から外れた)行動を
しなさっていたという。
ある時は、清水の滝の下に立ち寄って、合子〔=ふた付きの容器)という物に
水を入れて、陰部を洗いなさることが、日常的な行為であった。(また、)
非常に静かに心を澄ましなさる時もあったようです。
並一通りの僧ではなく見えなさいました。
澄み切った心の内側は、常に同じ才能と知恵を持っているけれども、外見上の
ふるまいは、数多く(常識とは)変わっていたのは、
(カ) よしなき人の思ひを、我のみ一方にはとどめじ
とお思いになったのだろうか。
この上人こそが、藤原道隆の追善供養の日に、法興院に籠って、夜明け前頃に
千鳥が鳴く声を聞きなさって、
(キ) 夜が明けたようだ。賀茂の河原で千鳥が鳴いている。今日も(また)
あっけなく日が暮れようとしている
と、詠んで、『拾遺和歌集』に収録されなさった。
夜が明けるやいなや、きっとあっけなく日が暮れてしまうだろうということ
〔=世の無常)を、以前から悟っていらっしゃったのだろう。
あの『拾遺集』
には円松上人として載っておりますのは、この上人(宝日上人)のことである。
[設問]
以下、今年の添削通信の合格者(理科二類)の再現答案を紹介しつつ、解説します。
(一) 傍線部ア・イ・エを現代語訳せよ。
ア
Aさん⇒驚きあきれるほどにやつれている(「やつれている」は減点)
木山⇒驚きあきれるほど質素でみすぼらしい身なりをしている
*現代語の「やつれる」には、病気や心労などでやせ衰えるの意がありますが、古語の『やつる』にはその意味はありません。直単B64にあるように、" 質素な身なりをする,目立たないようにする "の意味のみです。従って、答案に「やつれている」と書いてしまうと、現代語的には、病気や心労でやつれている、といった異なる意味に解釈される可能性が出てきます。Aさんの答案は、その点で減点されると思います。
原則的に、東大の傍線部解釈では、傍線部の表記をそのまま答案化するのではなく、何らかの言い換えた形で解答するのがセオリー(定石じょうせき)ですし、特に、このような短い傍線部解釈の場合はなおさらそうすべきです。Aさんとの直単チェックは本番入試の直前まで何度も何度も繰り返しましから、おそらく“ 「やつる」の意味は? " と問えば、正しく古語の意味を答えられたのではないかと思います。しかし、入試の現場では、現代語の「やつれる」のニュアンスに引っ張られて、そのままでもいける、と判断されたのではないでしょうか?
また、『やつる』は直単の訳にもあるように、多くは外形的な格好・姿・身なりなどの外的様子を現す単語ですから、答案にも「〜な身なり/姿/様子」などの語句が必要となります。
イ
Aさん⇒見間違いであろうか(正解)
木山⇒見間違いであろうか
*『ひがごと(僻事)』直単名43…間違ったこと。 古文公式7黒傘マーク〜にや…〜であろうか。直訳で言えば “ 間違った目であろうか " となり、それを通りのよい表現に直せば「見間違いであろうか」となります。
ウ
Aさん⇒仕方がなくてやめました(正解か?)
木山⇒しかたがなくそれで終わりになりました
別解⇒どうしようもなくそれきりになってしまいました(河合塾)
*『力(ちから)なし』E軍記5…しかたがない。『已(や)ム』漢単D27…終わる。Aさんの答案は、意味の上では問題がないように見えますが、文脈上に置いたとき、ややこなれない印象もあります。「やみ侍りけり」の『やむ・已(や)ム』の意味を言い換えずに、そのまま答案に使った点がこなれない印象の原因でしょうか?《ただし、意味の上では減点のしようがなく正解となるのではないかと思います》河合塾の答案にある “ それきり " とは、それだけで終わらせる、それ以上のことはなかったという意を表す表現です。
(二) 「かきくらさるる心地」(傍線部ウ)とは、何に対するどのような心情か、説明せよ。
Aさん⇒理科にはこの設問はありません。
木山⇒裸で物乞いをする僧が宝日上人であったことに対して、心を暗くする思い。
別解⇒清水寺の高僧であるはずの宝日上人のあさましい奇行に心を暗くする悲嘆。
*『かきくらす』A動14①…心を暗くする。直訳すれば “ 自然と心を暗くする心地 " となります。その原因は、直前の内容にあるわけですから、それを具体的に書いたものが私の答案です。別解では宝日上人の行動を「奇行」の一語で表現し、かつ、直後の「伏しまろびて=その場に倒れ伏して」という強い表現にあわせて “ 悲嘆 " という語を追加したものです。
(三) 「この事、限りなくあはれに覚え侍り」(傍線部オ)とあるが、語り手はなぜそのように感じたのか、説明せよ。
Aさん⇒出家しても衣服は捨てないものなのに、それまで捨て切った悟り深い上人に感心したから。(若干減点か?)
木山⇒一切の名利への執着を捨て切った真の出家者の姿だと思ったから。
別解1⇒俗世への一切の執着を捨てようとする陰徳の理想の姿を見たから。
別解2⇒上人が一切の執着を捨て切った深い境地に至っていると思われたから。
*今回の設問の中で一番書きにくい問題です。仏教説話の一類型としての『陰徳僧/陰徳聖』の背景知識を知らなければ、全く見当違いな答案を書いてしまう可能性があります。
例えば、「この事、限りなくあわれに覚え侍りけり」の『あわれに』の意味を、現代語のように “ 不憫でかわいそうな状態に対する同情や憐れみ ”と解して、「元来清水寺の高僧であった上人の惨めな零落ぶりをしみじみと物悲しく感じたから」などと、ネガティブな方向で答案化した受験生もかなりいたのではないでしょうか?
対策としては、陰徳僧説話は一つのパターン化された類型なのですから、説明に資する表現や言い回しなども含めて『木山の背景知識No.12』の記述をそのまま覚えてしまうことです。
*空の概念は一切の名利みょうり(栄達や誉れ)・名聞みょうもん(世間の評判)から離れることを要求しますが、そのような名利・名聞を捨てて、徳高い僧となり人々の尊崇の対象となってしまうことが、また一方では名利・名聞になってしまう、という矛盾に陥ってしまいます。
真の仏道者は、そのような名利・名聞の中に安穏としているわけにはいきませんから、そういう名利でさえも捨てなければなりません。
じゃあどうするのかというと、あえて狂気を演じ、不浄の中に身を置くいっかいの乞食僧の姿で俗世の底辺に生きていくとか、またはあえて僧侶が守るべき戒(かい)をやぶる破戒僧(はかいそう)のふりをしてまでも、名利への執着を捨て切ろうとするわけです。
上の文章の「真の仏道者」や、末尾の「名利への執着を捨て切ろうとする」などはそのまま答案に使えます。要するに、俗世の名利への執着を完全に捨て切ることが出家者としての理想であり、その為に、あえて無一物(むいちぶつ)の奇行の僧にまで身を落としている姿こそが真の仏道者の姿であるという理解です。ですから、この文脈での『あはれに』の意味は ” しみじみと心を打つ感動 " といったニュアンスになります。
ただし、本文中には「名利」の語句が出ていませんので、木山方式の背景資料を習得していない人にとっては「名利への執着を捨てる」などという言い回しは書けない可能性が高いでしょう。
その場合は、別解1にあるように「俗世への執着を捨てる」と書いても正解となります。また、たとえ本文中に「陰徳」という用語が使われていなくても、受験生が予めの知識として知っていれば「陰徳」という語を答案の中に使っても正答となるはずです。
別解2は、「名利」「陰徳」という語句を用いず、” 俗世への執着を捨てる " という方向でまとめた例です。 いずれにしても、それらが出家者としてのあるべき姿であるという感動の気分が伝わるような書き方にする必要があります。
Aさんの答案は、「捨て切った悟り深い上人に感心したから」と書いている点で的確に的を得ていますが、前半部分で衣服に焦点を当てすぎている点で、解釈の幅が狭くなっています。衣類を捨てたことは一例であり、地位や名誉、生活の糧などの俗世に関わる一切を捨てていることを含むように、より抽象化・一般化した書き方をすべきです。その点で若干減点されると思います。
(四) 「よしなき人の思ひを、我のみ一方にはとどめじ」(傍線部カ)とはどういうことか、説明せよ。
Aさん⇒理科にはこの設問はありません。
木山⇒つまらない俗人の尊崇の念を我が身に受け止めまいということ。
別解⇒凡俗の崇敬を一身に受けることを拒絶し敬われないようにしようということ。
*傍線部に至る文脈を確認してみましょう。「およそこの上人はもの狂わしい様をなさっていた。《中略》澄み切った心の内は、いつも同じ才知であるけれども、外見上のふるまいは、数多く変わっていたのは、カ) よしなき人の思ひを、我のみ一方にはとどめじとお思いになったのだろうか、という文脈。
『よしなし』C形82の意は「つまらない」。
『ひとかたに』は形容動詞「ひとかたなり」の連用形で、「ひたすら・一途に」。つまり、直訳すれば、『つまらない人の思いを、我が身ばかりにひたすらとどめまい』となります。
これは何を言っているのでしょうか?
その理解の為には、そもそも陰徳僧は何のために陰徳をなすのか、という根本を知る必要があります。古文背景知識No.12には「空の概念は一切の名利みょうり(栄達や誉れ)・名聞みょうもん(世間の評判)から離れることを要求しますが、そのような名利・名聞を捨てて、徳高い僧となり人々の尊崇の対象となってしまうことが、また一方では名利・名聞になってしまう、という矛盾に陥ってしまいます。真の仏道者は、そのような名利・名聞の中に安穏としているわけにはいきませんから、そういう名利でさえも捨てなければなりません」とあります。その ” 人々の尊崇の対象となってしまう " という部分を、「よしなき人の思い」に重ねてみて下さい。『よしなき人=つまらない人』とは、仏教的分脈では「俗人」のことであり、そのような俗人の尊崇の対象となり高僧として敬われてしまうことが、また一つの名利となるのであれば、そのような名利もまた拒絶しなければならない、というわけです。
つまり、傍線部の意味合いを噛み砕いて説明すれば、上人は『つまらない俗人からの尊崇の思いを、我が身に留めることはするまい(=受け止めることはしないようにしよう)』と思って、あえて破戒僧のふりをして奇行をなしていると解釈できます。
この設問もまた,背景知識のような予備知識がなければ、なかなかドンピシャの正答を書くのが難しい設問と言えます。どのような資料を持って受験の一年を過ごしたかが、結果を左右する一例と言えるでしょう。
(五) 傍線部キの歌は、どのようなことを表しているか、説明せよ。
Aさん⇒夜が明けて鳥が鳴いているが、日は暮れて、またはかなく無常な一日が過ぎるということ。(正解)
木山⇒夜明けがすぐに日暮れ鳴るように、人の世も移ろいやすく無常だということ。
*先に示した陰徳聖に関する背景知識を、再度、確認してみましょう。
『ところで、隠徳聖の話というのは、逆に言えば、隠徳に失敗した僧の話、つまりバカな乞食のように見えて、ひょっとした拍子には、実は徳高い僧なのではないか、と思わせる行動をとってしまうお話です。
それはたとえば、天台宗の難解な教理を見事に解き明かすとか、世の無常めいた言葉をさらりと言ってのけるとか〜〜〜〜〜そんなふうな結末になっていて、それに対する説話作者の感動が述べられます』
とあるように、今回の説話では宝日上人が勅撰集に詠んだ釈教歌(しゃくきょうか)が、その「世の無常めいた言葉」に当たるわけです。
夜が明けたと見ると、すぐに日が暮れてゆく、その仮そめの世の無常迅速なうつろいの速さを思えば、しみじみと世の無常を観ぜずにはおれない、といった意味の歌です。
釈教歌(しゃっきょうか)とは、仏教の教えや思想を和歌の形式で表現したものです。経典や教理を題材にしたり、法事や無常観を詠んだり、仏菩薩や高僧を賛嘆したりする歌が含まれます。
あの有名な鴨長明は、宝日上人のこの和歌によほど法味を観じて感動していたようで、「発心集」の中にこの歌を引用した上で、『和歌はよくことわりを極むる道なれば、これによせて、心を澄まし、世の常なきを観ぜんわざども便りありぬべし。(中略)聖教と和歌とは、はやく一つなりけり」とて、その後なむ、さるべき折々、必ず詠じ給ひける』とまで書いています。
というわけで、答案に必要なキーワードは " 世の無常 /仮そめの世/この世は儚く移ろいゆく" などの言葉が必要です。
![]()


第三問〔漢文〕
次の文を読んで、あとの設問に答えよ。
[書き下し文]
人(ひと)恒(つね)に執着を病(うれ)ふ。然(しか)れども亦(ま)た
a 不レ 可二 概 論一。
良(まこと)に学(がく)は好むを以(もっ)て成(な)り、之を好むの
極(きょく/きわみ)を着(ちゃく)と名(な)づくるに繇(よ)る。
羿(げい)は射に着し、遼(れう)は丸に着し、連は琴に着するかな。
《注…羿は弓、遼はお手玉、連は琴の名人として知られる》
夫(そ)れ弈(えき)《注…囲碁》に着する者は、屏帳垣牖(へいちょうえんゆう)
《注…牖は窓》皆森然(しんぜん)として《注…びっしりと》黒白勢を成(な)
すに、書(しょ)に着する者は、山中の木石(ぼくせき)尽(ことごと)く黒なるに
至(いた)り、馬を画(えが)くを学ぶ者は、馬現(あら)はるるに牀榻(しょうと
う)《注…ベッド》の間に至(いた)る。
夫(そ)れ然(しか)る後に其(そ)の芸を以て天下に鳴りて
b 声二 後 世一。
c 何 独 於二 学 道一 而 疑レ 之。
《注…学道はここでは仏道を学ぶこと》
是(こ)れの故に参禅(さんぜん)の人は、茶に茶を知らず、飯(はん)に飯を知ら
ず、行きて行くを知らず、坐(ざ)して坐するを知らず、筐(はこ)を発(ひら)き
て扉(とざ)すを忘れ、厠(かわや)を出て衣を忘るるに至る。
念仏の人は、目を開き目を閉(と)づるも、観(かん)前(まえ)に在(あ)り《注…
仏などを観想すること》心を摂(おさ)め心を散らすも念(ねん)恒(つね)に
一(いつ)なるに至る。
良(まこと)に情(なさけ)極(きは)まり志(こころざし)専(もっぱ)らにして、
功深く力(ちから)到(いた)るに繇(よ)りて、
d 不レ 覚 不レ 知、
忽(たちま)ち三昧(ざんまい)《注…深く集中した境地》に入るなり。
亦(ま)た燧(ひ)《注…火打ち石》を鑽(き)る者の、之を鑽(き)りて已(や)まず
して焔(ほのほ)を発し、鉄を煉(れん)する者の、之を煉(れん)して已(や)まず
して鋼(こう)を成(な)すがごときなり。
概(がい)して其(そ)の着(ちゃく)せんことを慮(おもんぱか)りて悠悠(いう
いう)蕩蕩(たうたう)《注…ゆったりと気ままなさま》、
e 如ク二 水ノ 浸スガ一レ 石ヲ、
年刧(ねんごふ)《注…長い年月》を窮歴(きゅうれき)すとも、何(なん)の益
(えき)か之(こ)れ有(あ)らん。
是(こ)の故に
f 執 滞 之 着ハ 不レ 可カラレ 有ル、 執 持 之 着ハ、
不レ 可カラレ 無カル。
[現代語訳]
人は常に執着(してしまうこと)を心配する。
しかしながら、また、
a 不レ 可二 概 論一。
(なぜなら)まことに、学問というものは好むことによって成し遂げられ、学問を好むことの究極を執着と呼ぶことに依(よ)るからです。
羿(げい…人名)は弓を射ることに執着し、遼(涼…人名)はお手玉に執着し、連(れん…人名)は琴に執着したことだなあ。
そもそも、囲碁に執着する者は、仕切りや垣根、窓などすべてに、びっしりと黒と白(の囲碁の石)の形勢を成しているように至り(=そのように見えるようになり)、書道に執着する者は、山中の木や石がことごとく(墨で書いた書の)黒に見えるようになり、馬を描くことを学ぶ者は、寝台の間(=夢)に馬の姿が現れるに至るのです。(=それほどまでに専念するものなのです)
そもそも、こうした後に初めて、その技芸によって天下に名声を鳴り響かせて、
b 声二 後 世一。
c 何 独 於二 学 道一 而 疑レ 之。
《注…学道はここでは仏道を学ぶこと》
そういうわけで、禅を学ぶ人は、お茶を飲んでいてもそのお茶を知らず(知覚せず)、ご飯を食べていてもそのことを知らず、歩いていても歩いていることを知らず、座っていても座っていることを知らず、箱を開けて閉ざすのを忘れ、便所から出て衣を(直し)忘れるに至るのです。(=それほどに禅に没入するべきなのです)
念仏を唱える人は、目を開けていても閉じていても、眼前に仏を観想《=対象に心を集中し、静かに思いをこらすこと》し、心を治めていても散漫になっても、その念は常に(念仏)一つに至るのです。
まことに、感情が極まって志が一つに専念して、修行の功が深まり、力が(十分に)到達することによって、
d 不レ 覚 不レ 知、
たちまちに三昧《ざんまい=深く集中した境地》に入るのです。
(これも) また、まるで火打石を打つような者が、火打石を打つのを止めずに炎を起こしたり、鉄を精錬する者が、鉄を精錬するのを止めずに鋼を生成したりするようなものです。(一心に専心することで物事が成就することの喩えか?)
一般的に(総じて)、自分が執着してしまうことを思案して(心配して)、のんびりゆったりと気ままに(仏道を)学ぼうとするのは、
e 如ク二 水ノ 浸スガ一レ 石ヲ、
長い年月を極め尽くしたとしても、何の利益があるだろうか。いや、まったく利益は無い。
こういうわけで、
f 執 滞 之 着ハ 不レ 可カラレ 有ル、 執 持 之 着ハ、
不レ 可カラレ 無カル。
[設問]
(一) 傍線部a・b・dを平易な現代語に訳せ。
a
Aさん⇒ 一概には言えない(正解)
木山⇒一概に論じてよいわけではない
*まず、傍線部aの直前の「人恒(つね)に執着を病(うれ)ふ」とは、仏教的背景を踏まえた発言です。なぜ仏教は執着を厭(いと)うのかについては、このホームページにも載せられている『古文背景知識No.1空の概念』をお読み下さい。詳しく説明しています。とにかく、一般的に仏教に於いては物事に捉われて執着することを忌避する前提があり、その前提を述べた上で、しかしながら、やはり(すべての執着を)『概論(がいろん)すべからず』と言っているわけです。
概論とは「全体の内容をまとめて述べること、又は、そのようにまとめて述べたもの」という意味ですから、 ” ひとまとめにして論ずべからず " ということになります。後(あと)に打ち消しを伴って副詞的に用いられる『一概に〜すべきではない』などの表現も想起されるでしょう。
「可(べ)カラズ」の「可(べ)シ」の意味は、可能ではなく、適当の意と解釈すべきです。この文脈は一概に論ずることの当否/適不適を言っているのですから、出来るかどうかという可能の意にはなりません。
適当の訳は『〜するのがよい』(古文公式10)ですから、直訳は『ひとまとめに論じてよいわけではない』となります。
b
Aさん⇒ 後世に名声が伝わる(正解)
木山⇒後世に名声を残す
*直前の文脈は、学芸の道も専念して取り組む執着心があってこそ、はじめて天下に鳴りて『後世ニ声ス』というわけですから、「声」が ” 名声 "や ”名を残す " ことを意味することは容易に理解できただろうと思います。
d
Aさん⇒ 何も思わず、何も考えず(不正解)
木山⇒知らず知らずのうちに
*傍線部dの数行前に書かれた参禅の人の「行きて行くを知らず、座して座するを知らず」という表現は、参禅修行への専念を表すと同時に、それらの行為が自意識を超えた無我の境地で行われていることをも表しています。そして、その没入的無我の境地が、傍線部dの直後の『三昧(ざんまい)…雑念を去り対象に没入する状態』の境地にもつながっていくわけです。
そういう文脈の中で『覚えず知らず』を解釈すれば、 ” 無意識のうちに、知らず知らずのうちに、無意識の没入 " といったニュアンスになると思います。一種の慣用的表現でもあり、説明を聞いてしまえば簡単に感じますが、Aさんも失点しているように、意外につかみにくい設問であるのかもしれません。
(二) 「何 独 於二 学 道一 而 疑レ 之」(傍線部c)を、「之」の内容がわかるように、現代語訳せよ。
Aさん⇒ どうして仏道を学ぶことにおいてのみ、好いていることを極めて名声を得るということを疑うのか、いや、疑う必要はない。(一部減点だがほぼ正解)
木山⇒どうして仏道を学ぶことに於いてだけ好むことによる執着に懐疑的になる必要があろうか、いや、ない。
*直前に書かれている三つの具体例をざっくりまとめると、囲碁に着〔執着〕する者が何でも黒白(の囲碁の石)に見えるように、書道に着〔執着〕する者が何でも(墨で書いた書の)黒に見えるように、馬の絵を描くことを学ぶ者が馬が夢に現れるように、いつでもどこでも専念せよという教えです。その具体例を受けて、夫(そ)レ而(しか)ル後(のち)ニ《そもそもそうやってのちにはじめて》後世に名を残すことが出来るのだ、という文脈。
専念することは対象に執着する事にもつながりますから、学芸において執着が積極的に肯定されるものならば、仏道においても同様ではないか、というのが筆者の主張となります。
傍線部cの正しい読み方は、公式17A②の『独(ひと)リ〜〜〜〜ノミ』の限定句形が否定詞に返る場合の公式17左*累加形『独(ひと)リ〜〜〜〜ノミナラず』を基本として、それを否定詞ではなく、反語の句形で表すことになります。
正しい読み方は、 " 何(なん)ぞ独(ひと)り学道に於(おい)てのみ之(これ)を疑(うたが)はんや " です。
直訳は『どうして、ただ仏道を学ぶ〔補註あり〕ことに於いてのみ、これ《=執着》を疑うことがあろうか、いや、疑う必要はない』。
「之(これ)」は直接的には前文の「着〔執着〕」を指しています。ただし、仏道における専念執着は、俗世の名声を得ることを目的にして行うものではありませんから、Aさんの答案中の「名声を得る」の部分は明らかな減点となります。
出家の理念は俗の名利・名聞を離れることにあることは常識ですし、Aさんの答案のように書きますと、本来捨てるべき俗世の名聞(みょうもん)まで肯定してしまうことになってしまいます。単に「好きを極める専心という執着心は仏道にも必要だ」と書けば正解ですが、「名声という俗世の名聞まで否定されるものではない」と書くのは行き過ぎです。
諸解答の中にはAさんの答案のように「執着」の語句を用いず、「好むこと/好んで極めること」とするものがありますが、これは冒頭近くに出てくる『学は好むを以て成り、之を好むの極(きわみ)を着と名づく』を受けたものです。許容されると思います。
(三) 「如二 水 浸一レ 石」(傍線部e)とはどういうことか、簡潔に説明せよ。
Aさん⇒ 理科にこの設問はありません。
木山⇒水が石を浸しても変化がないように長い年月を無益に過ごすこと。
別解⇒長い年月をただゆったりと気ままに無益に過ごすこと。
*傍線部eの前後を訳せば、「一般にその執着することを心配して、ゆったりと気ままに過ごすのはe水が石を浸(ひた)すがごとく、長い年月を極め尽くしても何の益があろうか、いや、何の益もない」となりますから、傍線部eの比喩は何かしら ” 無益なことの比喩 "であるはずです。
水に石を浸しても変化が生じない、というのは、確かに静止した水であれば石には変化が生じないという理解でしょうか。『雨垂れ石をも穿(うが)つ』という「漢書」の一節や、グランドキャニオンもコロラド川の水の侵食により・・などと言えば、たとえ岩や石であっても侵食されますが、それらは水の運動や衝撃によるのであって、静かに動かない水の中に石を浸す場合には何の変化も生じない、という解釈なのではないかと思います。
(四) 「執 滞 之 着 不レ 可レ 有、執 持 之 着
不レ 可レ 無」(傍線部f)とはどういうことか、本文の趣旨を踏まえて説明せよ。
Aさん⇒ ただ執滞してゆったりときままに過ごすことは良くないが、好むことに執着して極めることは良いことだ。(正解だが一部減点)
木山⇒仏道の修得には滞ってしまう執着ではなく、好んで追い求める執着を保持することが不可欠だということ。
別解⇒仏道を極めるには漫然と修行しても効果はなく、対象への専心を保持しなければならない、ということ。
*「無かるべからず」の直訳は、『なくてよいわけではない』、つまり、『必要であり、なくてはならない』の意ですから、全体の直訳は、 ” 執滞の着〔執着〕はあってはならないが、執持の着〔執着〕はなくてはならない "となります。
執滞の「滞」の字義は『とどこおる/とどまって進まない』ですから、とどこおって進まないような執着心はよくない、ということでしょうか。
一方の「執持」とは ” 執着を保持する " 意のようですが、字義から解釈するよりも、全体の主旨を踏まえれば、冒頭近くに出てくる『学は好むを以て成り、之を好むの極(きわみ)を着と名づく』などから、” 好んで極める専心の態度 " を「執持」という語句に込めているのではないか、と解釈できます。
私がAさんの答案を一部減点としたのは、この一文は仏道に関する提言であるのに、その点を踏まえていないと感じたからです。
そもそも、冒頭にあるように「人は恒(つね)に執着を病(うれ)ふ」というのは仏教的背景を前提にした発言であって、それ以外の学芸の道であれば、書道にせよ画道にせよ、別に執着心があっても問題はなく、むしろ大いに結構なのではないでしょうか?
一般に執着を忌避すると言われる仏道であればこそ、あえて執着を是とする面もあるとする筆者の提言に意味があるわけですから、やはり、この答案には ” 仏道において〜/仏道の修得には〜 "などの前提が必要だと思います。
代ゼミの答案のみ『学芸を極めるのに〜』と始めていますが、以上の理由から私は一部減点の可能性があると思います。